2025年09月12日 更新
混同しやすい?SESと業務委託の2つの違いや特徴をやさしく解説
- オフィス向け

- SESとは?業務委託との違いや他の契約形態との違いをわかりやすく解説
- 業務委託と労働者派遣の法律上の違いとは?基本を押さえておこう
- IT業界で使われる契約形態一覧|特徴と使い分けを解説
- 業務委託と請負契約の違い|成果物と責任範囲に注目
- 業務委託と委任契約の違い|指揮命令と報酬の関係を知る
- SES(業務委託)で働く人の年収相場はどれくらい?
- 正社員として働くSESエンジニアの年収はどのくらい?
- フリーランスSESエンジニアの年収相場と収入の特徴とは?
- SES(業務委託)契約で得られるメリットとは?【法人向け】
- 社内リソースに縛られず、必要な業務に集中できる
- 他社エンジニアとの協業でプロジェクトに多様性が生まれる
- 正社員採用よりも導入ハードルが低く柔軟に活用できる
- SES(業務委託)契約のデメリットと注意点【法人向け】
- トラブル時に相談しづらい環境がある可能性
- SES(業務委託)契約で失敗しないための注意点と事前対策【法人向け】
- 1. 法的な立場と契約内容をしっかり理解しておく
- 2. 「面接」ではなく「顔合わせ」や「職場見学」で調整する
- 3. 勤務条件(定時・休憩など)の取り決めを明確にしておく
- 4. SES契約を活用する際は中長期的な人材戦略を意識する
- まとめ:SESと業務委託の違いを理解して、自社に合った選択を
IT業界で人材を活用しようとしたとき、よく出てくるのが「SES」と「業務委託」という言葉です。
どちらも外部人材を活用する方法ではありますが、実は契約内容や働き方、責任の範囲などが大きく異なります。
この違いを正しく理解していないと、
「期待していた働き方と違った…」
「法的なトラブルにつながってしまった…」
といった事態にもなりかねません。
この記事では、SESと業務委託の関係性や違いをわかりやすく整理し、企業が自社に最適な人材活用の形を選べるようになるための実践的なヒントをお届けします。
契約形態の選び方に悩んでいる方、初めてSESに関わる方も、この記事を読めば基礎から応用までしっかり理解できるはずです。
SESとは?業務委託との違いや他の契約形態との違いをわかりやすく解説

IT業界でよく聞く「(システムエンジニアリングサービス)」と「業務委託」。
どちらも外部人材を活用する方法の一つですが、その契約形態や働き方には大きな違いがあります。
さらに、業務委託の中にも「請負」「委任」「準委任」など、複数の種類が存在し、それぞれに法的な意味合いや責任範囲が異なります。
ここでは、SESがどのような契約形態なのかを整理したうえで、業務委託や派遣との違い、そしてIT業界での一般的な契約形態を比較しながら、混同しやすいポイントを明確に解説していきます。
業務委託と労働者派遣の法律上の違いとは?基本を押さえておこう

まず押さえておくべきは、労働者派遣と業務委託はまったく別物であるという点です。
- 労働者派遣
派遣元企業と雇用契約を結んだ社員が、派遣先企業の指揮命令を受けて働きます。
指揮命令系統は派遣先にあり。 - 業務委託
あくまで成果物や業務の遂行自体を外部の企業に任せる契約で、業務を依頼するだけで、指揮命令はしてはいけません。
2つの違いを理解していないと、「偽装請負」と呼ばれる違法行為に発展する可能性があり、企業側にも大きなリスクが生じます。
IT業界で使われる契約形態一覧|特徴と使い分けを解説
IT業界では、人材の活用に応じて以下のような契約形態が使い分けられています。
| 契約形態 | 概要 | 指揮命令 | 成果責任 | 契約先 | 主な用途 |
| 正社員雇用 | 自社直接雇用 | 自社 | あり | 自社 | 長期的な戦力確保 |
| SES(準委任) | 業務遂行に対する契約 | 客先 | なし(遂行義務のみ) | SES企業 | 技術支援・常駐作業 |
| 業務委託(請負) | 成果物納品に対する契約 | なし | あり | 外注先 | システム開発等の外注 |
| 派遣 | 派遣先で労働提供 | 派遣先 | なし | 派遣会社 | 短期的な労働力補充 |
SESは、業務委託の一種(準委任)であり、委任と請負の中間的な位置付けにあります。
業務委託と請負契約の違い|成果物と責任範囲に注目

業務委託の中でも「請負契約」は、成果物の完成に対して報酬が支払われる契約です。
たとえば「このシステムを納品してほしい」といった場合、その完成に対して責任が発生します。
一方、SESのような準委任契約では、「成果」ではなく「業務の遂行」に対して報酬が支払われるため、仮に開発が遅れても業務を遂行していれば報酬は発生します。
契約時点での責任範囲・成果管理・スケジュール管理の考え方に直結するため、契約形態に応じたマネジメント設計が不可欠です。
業務委託と委任契約の違い|指揮命令と報酬の関係を知る

委任契約とは、主に「法律行為」や「対外的な手続き」を代理で行う契約を指します。
SESとは異なり、専門性よりも法律行為の代理や交渉事務などに使われる契約です(例:顧問弁護士への依頼など)。
SESで採用されるのは「準委任契約」であり、専門スキルを用いた事務作業や開発業務などを対象とするケースがほとんどです。
つまり、業務内容が異なれば適用すべき契約形態も異なるため、委任・準委任の違いは企業側にとっても知っておくべき知識です。
SESは業務委託契約の一種(準委任契約)に該当し、請負契約や労働者派遣とは本質的に異なる契約形態です。
それぞれの契約形態には、指揮命令の有無や成果責任、契約相手との関係性といった違いがあり、法的な観点からの理解と適切な使い分けが非常に重要になります。
とくにIT業界ではSESが一般的に活用されていますが、他の契約形態との違いをきちんと理解しておくことで、トラブルの予防や最適な人材活用の実現につながります。
SES(業務委託)で働く人の年収相場はどれくらい?

SESとして働くエンジニアは、雇用形態によって収入に大きな差が出るのが特徴です。
特に「正社員」としてSES企業に属する場合と、「フリーランス」として案件ごとに契約する場合とでは、報酬体系・保障・交渉力などがまったく異なります。
このセクションでは、それぞれの年収相場や収入の仕組み、メリット・注意点を整理し、自分に合った働き方を考えるヒントを提供します。
正社員として働くSESエンジニアの年収はどのくらい?

SES企業に正社員として雇用される場合、年収は300万〜500万円前後が一般的なレンジです。
月給に換算すると、25万〜35万円前後+賞与(業績に応じて)というケースが多く見られます。
【特徴】
- 安定性がある – 社会保険や有給休暇、福利厚生が整っている
- スキルよりも勤続年数が評価される傾向がある
- 単価と給料の乖離が起こりやすい(=自分の売上に対して報酬が低く感じられることも)
企業によっては、客先常駐で高単価案件に入っていても、給与テーブルが固定のため収入に反映されにくいことが悩みの種となることもあります。
フリーランスSESエンジニアの年収相場と収入の特徴とは?

フリーランスとしてSES契約を行う場合、年収600万〜900万円超も珍しくありません。
案件の単価は月60万円〜80万円前後がボリュームゾーンで、高スキル人材であれば月100万円以上も可能です。
【特徴】
- 自分で単価交渉できるため、収入が反映されやすい
- 福利厚生や社会保障は自分で対応する必要がある
- 空白期間(案件がない月)が収入ゼロになるリスクも
自由度は高い一方、営業・契約管理・確定申告などの業務も自分で行う必要があります。
そのため、「技術力」だけでなく、「自己管理能力」や「マーケット理解」も求められます。
SESエンジニアの年収は、正社員かフリーランスかによって大きく異なるのが実情です。 安定を重視するなら正社員、報酬の最大化を狙うならフリーランスが選ばれやすい傾向にあります。
とはいえ、それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分のライフスタイルや将来のキャリアプランに合った働き方を選ぶことが大切です。
SES(業務委託)契約で得られるメリットとは?【法人向け】

SES(システムエンジニアリングサービス)契約には、「必要なときに必要なスキルを確保できる」「幅広い技術をプロジェクトに投入できる」といった法人にとっての大きな利点があります。
自社で人材採用を行うには時間やコストがかかる一方、SESを活用すれば即戦力となるエンジニアを柔軟に確保でき、開発リソースの強化や事業のスピードアップにつなげることができます。
ここでは、SES契約を通じて企業が得られる代表的なメリットを3つに絞って解説します。人材戦略を考える際の参考にしてください。
社内リソースに縛られず、必要な業務に集中できる

SES契約では、エンジニアはSES企業に所属しながら、クライアントである発注企業に常駐して業務を行います。
この仕組みによって、自社の正社員を教育・雑務対応に割かずに済み、プロジェクトごとに必要な技術業務へ人材を集中投入できるのが大きな利点です。
たとえば、社内SEや自社開発メンバーが日常業務に追われている場合でも、SES人材を投入することで「開発・保守に専念できる体制」をすぐに整えることができます。
結果として、自社社員はコア業務に集中しやすくなり、全体の生産性向上にもつながります。
他社エンジニアとの協業でプロジェクトに多様性が生まれる

SESは複数の企業からエンジニアが集まることが多いため、多様な技術背景や開発ノウハウを持つ人材がチームに加わることになります。
これにより、
- 最新のフレームワークや開発手法を持ち込んでくれる
- 他社での成功事例や改善ノウハウを共有してくれる
- チーム内での知識交換・勉強会を通じて、社内人材も刺激を受ける
といった効果が期待できます。
SES活用は単なる「人手の補填」にとどまらず、社内だけでは得られない知見を取り込む機会としても有効です。
正社員採用よりも導入ハードルが低く柔軟に活用できる

IT人材を正社員で採用する場合、採用コストや教育コストがかかり、ミスマッチのリスクもあります。
一方、SES契約は「プロジェクト単位・期間限定」での活用が可能であり、短期的なリソース確保から長期的な体制強化まで柔軟に対応できます。
さらに、必要なスキルセットを持った人材をスピーディーにアサインできるため、採用活動に時間を割くことなく、即戦力を投入できるのも大きな魅力です。
SES契約には、法人にとって以下のようなメリットがあります。
- 必要な業務に集中できる体制を構築できる
- 他社のノウハウを取り込み、プロジェクトに多様性を生む
- 正社員採用に比べてハードルが低く、柔軟に活用できる
人材不足が深刻化する中で、SESは「即戦力人材を確保しつつ、自社の人材戦略を柔軟に設計できる手段」として有効です。
ただし、自由度が高い分、契約内容の管理や現場環境の整備には法人側にも責任が伴います。
次のセクションでは、SES契約を導入する際の注意点やリスクについても確認していきましょう。
SES(業務委託)契約のデメリットと注意点【法人向け】
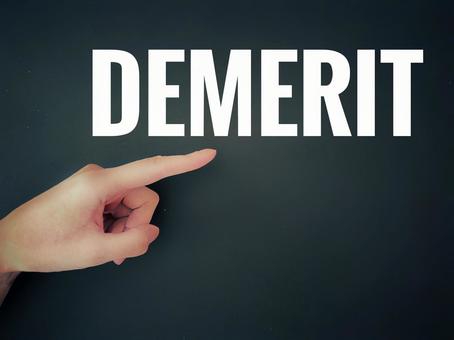
SESは柔軟で実務経験が積みやすい一方で、正社員雇用や自社勤務とは異なる特有のデメリットもあります。
とくに常駐型であること、指揮命令権が客先にあることなどが、環境の不安定さにつながる場合も。
ここでは、SES契約でありがちな課題と、その背景にある構造的な要因について解説します。
事前に知っておくことで、入社後のギャップやミスマッチを防ぎやすくなるでしょう。
トラブル時に相談しづらい環境がある可能性

SES契約では、エンジニアが企業に常駐してプロジェクトに従事するのが基本です。
この業務スタイルの影響で、トラブルや課題が発生した際は、企業内でその場の判断や対応を迫られることが多く、馴染みがなく相談しにくい環境に置かれがちです。
たとえば以下のようなケースが考えられます。
- クライアント側の指示に無理がある
- 人間関係やハラスメントなどの職場環境に問題がある
- 業務内容が当初の契約と食い違っている
こうした状況でも、SESエンジニアは日々の業務指示をクライアントから受けているため、自社との日常的な接点が少なく、距離が広がりやすいのが実情です。
また、自社に相談したとしても、常駐先に社員がいないため現場の状況が「伝聞」でしか把握できず、的外れなアドバイスや時間のかかる対応になってしまうことも珍しくありません。
エンジニア自身が「どうせ相談してもムダ」と感じてしまえば、トラブルを抱え込んでしまうリスクも高まります。
このように、トラブル対応やコミュニケーションにかかるコストが大きい点は、SES契約の構造的な弱点といえるでしょう。
相談しやすい制度やメンター体制を整えておくことが非常に重要となります。
SES(業務委託)契約には、働く環境が客先に依存するという構造的な事情から、相談しづらさ、トラブルの抱え込みといった課題がつきものです。
これらはすべて「仕組み上の特徴」であり、エンジニア本人の努力だけでは解決が難しい場合もあります。
だからこそ、事前にフォロー体制や働く環境をしっかり整えておくことが、SES契約の正しい人材活用につながるポイントです。
SES(業務委託)契約で失敗しないための注意点と事前対策【法人向け】

SES契約は、自社のリソース不足を補い、必要なスキルを持つエンジニアを柔軟に活用できる点で大きなメリットがあります。
しかし一方で、契約形態の複雑さや業務範囲の曖昧さによって「期待した成果が得られなかった」「法的トラブルに発展した」といったケースも少なくありません。
だからこそ、法人がSES契約を活用する際には、契約の基本を理解し、常駐先での管理体制や環境を適切に整備しておくことが重要です。
ここでは、SES契約で失敗を防ぐために知っておきたいポイントを4つに分けて解説します。
1. 法的な立場と契約内容をしっかり理解しておく

SES契約は、労働者派遣契約や請負契約とは異なる「準委任契約」として扱われるのが一般的です。
つまり、成果物の納品ではなく「業務を遂行すること」に対して報酬が発生する契約形式です。
法人側がこの仕組みを正しく理解していないと、SESエンジニアに直接業務命令を出したり、自社の就業規則を強制したりすることで「偽装派遣」とみなされるリスクがあります。
また、契約内容が不明確なまま運用すると、以下のような問題につながる恐れがあります。
- SES企業ではなく自社が勤怠管理や日報提出を強制してしまう
- 実質的に派遣契約と同じような指揮命令関係が発生する
このような事態を避けるために、法人は必ず契約書や業務委託範囲を明確化し、**「指揮命令権はSES企業にある」**という原則を遵守することが求められます。
2. 「面接」ではなく「顔合わせ」や「職場見学」で調整する

SES契約では、労働者派遣との違いを明確にするため、契約前に「面接」という言葉を使うことは避けるのが一般的です。
それぞれの言葉の代わりに、以下のような表現が用いられます。
- 顔合わせ
- 職場見学
- 事前説明会
法的に「事前面接を行えば偽装派遣の疑いが高まる」ためであり、法人側も注意すべき点です。
もしクライアント側から「面接」という言葉を使ってしまうと、後々の監査でリスクが指摘される場合もあります。
法人としては、**「候補者のスキルや経歴を確認するための情報共有の場」**として位置づけ、形式上・用語上のルールを徹底することが重要です。
3. 勤務条件(定時・休憩など)の取り決めを明確にしておく

SES契約では雇用主はSES企業である一方で、エンジニアの勤務実態はクライアント企業内で発生します。
このため、労働時間や休憩、残業の有無といった条件が不明確だとトラブルの原因になります。
法人側で特に確認・取り決めしておくべき点は以下のとおりです。
- 実際の勤務時間・休憩時間
- 残業や休日出勤の有無と申請方法
- テレワークの可否
- 服装や入館ルールなど職場規律
こうしたルールを事前にSES企業とすり合わせ、契約書や覚書に明記することで、現場での認識齟齬を防ぎ、エンジニアが働きやすい環境を整えられます。
4. SES契約を活用する際は中長期的な人材戦略を意識する

SESは即戦力を確保する上で有効ですが、契約ごとに案件が変わるため、長期的なスキル蓄積や育成は難しい側面があります。
法人としても「SESでどの領域を補完し、どの範囲を自社内で強化するのか」を明確にすることが重要です。
例えば、
- 一時的な開発要員の確保
- 自社社員の育成期間中の戦力補填
- 特定分野(セキュリティ、クラウドなど)の専門スキル補完
といった目的を明示し、SES活用を中長期的な人材戦略の一部として設計することで、コスト対効果を高められます。
SES契約は便利な仕組みですが、法人側が契約形態や管理方法を誤解すると、法的リスクや現場トラブルにつながります。
法人が押さえるべきポイントは以下の4点です。
- 法的立場と契約内容の正確な理解
- 「面接」ではなく「顔合わせ」など適切な形式での調整
- 勤務条件の事前確認と契約への明記
- SES活用を自社の人材戦略の一部として設計
これらを徹底することで、SES契約を安全かつ効果的に活用でき、エンジニアにとっても働きやすい環境を整えることが可能になります。
まとめ:SESと業務委託の違いを理解して、自社に合った選択を

SESと業務委託は、どちらもIT業界で広く使われている契約形態ですが、法的な立場・業務範囲・働き方などに明確な違いがあります。
表面的には似ていても、その内側の仕組みや働く現場での実態には、大きなギャップが存在するため、正しい理解がなければ「ミスマッチ」や「契約トラブル」につながるリスクもあります。
この記事では以下のようなポイントを詳しく解説しました。
- SESと請負・派遣など他の契約形態との法的な違い
- 正社員・フリーランスそれぞれのSES年収相場
- SES契約のメリットとデメリット【法人向け】
- 契約時に注意すべき点と事前確認のコツ【法人向け】
最適な人材活用を実現するためには、「契約形態」も人材戦略の一部であると捉え、目的に合った形を選ぶことが重要です。
SESを導入・利用する側も、そこで働くエンジニア自身も、お互いの理解を深めることで、より健全で持続可能な関係を築くことができるでしょう。
SESと業務委託の違いを見極め、自社や自分自身にとって最適なキャリア・契約選択をするための一助になれば幸いです。
関連キーワード









