2025年09月14日 更新
【SES】客先常駐と派遣の仕組みと見極め方を法人向けに解説
- オフィス向け

- 客先常駐とは何か?
- 客先常駐の定義と働き方の特徴
- SES・派遣・請負における客先常駐の意味の違い
- 客先常駐の主な業務内容と対象職種
- 派遣とは何か?
- 労働者派遣の概要と契約の仕組み
- 一般派遣と特定派遣の違い(※法改正を踏まえた記述)
- 派遣先・派遣元の責任範囲と法的義務
- 客先常駐と派遣の違い
- 指揮命令権の所在と業務指示の違い
- 雇用関係の有無と契約形態の違い
- 稼働内容や責任範囲の相違点
- 法的区分とそれぞれに適用される法律(労働者派遣法/民法など)
- SES契約・請負契約との違いも理解しよう
- SES契約の特徴(準委任契約)と指揮命令の制限
- 請負契約との明確な違いと成果物責任
- 客先常駐との混同による「偽装派遣」リスクの防止
- 客先常駐と派遣のメリット・デメリット比較
- 法人側から見たメリットと活用シーン
- 雇用・契約の柔軟性とその制限
- 社内文化の浸透・教育・情報管理上の課題
- 客先常駐や派遣を導入する際の注意点
- 契約前に整理すべき指揮命令・責任範囲
- 情報セキュリティや社外秘保持の体制づくり
- 現場の受け入れ体制とオンボーディング支援の重要性
- 自社に最適な契約形態を見極めるためのポイント
- 短期プロジェクトと長期常駐の使い分け方
- 請負・派遣・SESのハイブリッド活用例
- 法令遵守とコンプライアンス体制の強化
- 現場で起きやすい誤解とトラブル事例から学ぶ契約形態の選び方
- 「派遣だと思っていた」が引き起こす偽装請負リスク
- 指揮命令の境界が曖昧な現場での混乱事例
- 稼働中のエンジニアが突然交代する背景と対応策
- 契約形態の違いを正しく理解し、最適な選択でリスクを回避する
「この契約って派遣?それともSES?」「指示は出してもいいの?」
そんな戸惑いを現場で感じたことはありませんか?
IT業界やエンジニアリング分野で頻繁に使われる「客先常駐」という働き方は、実は派遣・SES・請負など複数の契約形態と密接に関係しています。
しかし、それぞれの違いや法的な位置づけを十分に理解しないまま契約や業務が始まると、偽装請負や指揮命令違反といったリスクを招くことも。
本記事では、以下のような法人担当者の疑問に応えるべく、「客先常駐と派遣の違い」を中心に、制度的な仕組み・契約リスク・現場の管理ポイントまでを網羅的に解説します。
- 客先常駐とは何か?派遣との違いは?
- 指揮命令権はどこにあるのか?
- SESや請負契約との違いをどう見分ければよいのか?
- 自社にとって最適な契約スタイルはどれか?
トラブルを未然に防ぎ、適切な人材活用と法令順守を両立させるために。
このコラムを通じて、現場で混乱しないための正しい知識と判断力を身につけていただければ幸いです。
SESの導入・契約でよくあるトラブルなどもこちらにまとめているので、ぜひ御覧ください。
客先常駐とは何か?

IT・技術業界において頻繁に耳にする「客先常駐」という言葉。
しかし、その定義は曖昧なまま使われることが多く、契約形態や指揮命令の誤解からトラブルが起きるケースも少なくありません。
この章では、客先常駐という働き方の基本的な意味と仕組み、そしてSES・派遣・請負との関連性について明確にしていきます。
客先常駐の定義と働き方の特徴
客先常駐とは、自社に所属するエンジニアや技術者が、取引先企業(=クライアント)の現場に出向いて業務を行う働き方です。
常駐先はクライアント企業のオフィスや開発拠点であり、自社オフィスではありません。
主な特徴は以下の通りです。
- 勤務場所は常駐先(クライアント)
- 指揮命令の権限は契約形態により異なる
- プロジェクト単位、あるいは契約期間に応じた業務従事
この「常駐」という言葉自体は働き方を示しているにすぎず、契約形態を特定するものではありません。
つまり、「客先常駐=派遣契約」とは限らず、SES契約や請負契約でも常駐業務は発生します。
SES・派遣・請負における客先常駐の意味の違い

「客先常駐」と一口に言っても、契約形態によって実務上のルールや責任の所在が異なる点に注意が必要です。
| 契約形態 | 指揮命令権 | 成果物責任 | 法的枠組み | 常駐業務との関係 |
| SES(準委任) | SES企業側 | なし | 民法上の準委任契約 | よく用いられる |
| 派遣 | 発注元(クライアント) | なし | 労働者派遣法 | 客先常駐が前提 |
| 請負 | 請負会社側 | あり | 民法上の請負契約 | 常駐することもあるが限定的 |
たとえば
- SES契約では、エンジニアは常駐先にいながらもSES企業(元請)から業務指示を受けるべき
- 派遣契約では、エンジニアは常駐先の社員から業務指示を受けることが法律で許容されている
- 請負契約では、成果物完成が目的であり、指揮命令はクライアントが直接出すべきではない
このように、「常駐している」ことは共通していても、法的枠組み・役割・責任は契約形態により大きく異なります。
客先常駐の主な業務内容と対象職種

客先常駐で従事する業務は、IT業界を中心に技術職・開発職・保守運用職などが中心です。
業務内容は企業によって異なりますが、代表的なものは以下のような分野です。
- システム開発(Webアプリ、業務システム、基幹系など)
- インフラ構築・ネットワーク運用保守
- テスト・検証・デバッグ作業
- ヘルプデスク・ITサポート
- PMO支援・上流工程の補助
対象職種としては以下のようなエンジニアや技術者が多く見られます。
- システムエンジニア(SE)
- プログラマー(PG)
- インフラエンジニア
- テストエンジニア
- テクニカルサポート
- プロジェクトマネージャー補佐 など
現場のニーズに応じて柔軟にスキル人材を配置できることが、客先常駐の強みであり、またトラブルの温床ともなり得る要素です。
「常駐=派遣」ではない。契約形態による違いの理解が鍵
「客先常駐」という働き方は、あくまで“働く場所”を示す言葉にすぎません。
その裏にある契約形態を理解せずに運用すると、労働法違反や偽装請負といった法的リスクに直結します。
本章での要点を整理すると以下の通りです。
- 客先常駐はSES・派遣・請負すべての契約で起こりうる
- 指揮命令権の所在や成果責任の有無は契約形態によって異なる
- 同じ現場で働いていても、契約により立場やルールが大きく異なる
次章では、もうひとつの主役「派遣契約」について、仕組みや注意点を詳しく解説していきます。
違いを明確に理解し、自社にとって最適な人材活用方法を見極めるヒントを掴んでください。
派遣とは何か?

「派遣」という言葉は広く使われていますが、労働者派遣法に基づく法的な意味を正確に理解していないまま運用されているケースも少なくありません。
特に客先常駐と混同されやすく、「指揮命令は誰が行うのか?」「契約上の責任はどこにあるのか?」といった誤解が、偽装請負や法令違反といったトラブルに発展することもあります。
この章では、派遣契約の定義・契約構造・法的義務の全体像を法人視点で解説します。
労働者派遣の概要と契約の仕組み
労働者派遣とは、派遣元企業に雇用されている労働者が、派遣先企業の指揮命令のもとで働く契約形態です。
SESとの最大の違いは、業務の指示を出す権限(指揮命令権)が派遣先にあるという点です。
派遣契約の構造は以下のようになります。
- 雇用契約:労働者と派遣元企業の間に存在
- 派遣契約:派遣元企業と派遣先企業の間で締結
- 業務指示:実際の業務指示は派遣先企業から行う
派遣契約には、労働者派遣法という法律が厳格に適用されるため、契約期間・業務範囲・賃金格差是正措置など、細かい法規制が存在します。
一般派遣と特定派遣の違い(※法改正を踏まえた記述)

かつて存在した「一般派遣」と「特定派遣」は、2015年の労働者派遣法改正により統一されました。
現在では、すべての派遣事業者が許可制(=旧・一般派遣)に一本化されています。
違いのポイント(法改正前の参考情報含む)
| 区分 | 特徴(旧制度) | 現在の取り扱い |
| 特定派遣 | 常用雇用者のみを派遣でき、許可不要 | 廃止(新規参入不可) |
| 一般派遣 | 登録型の派遣も可能、厚労省の許可制 | 現在はこちらに一本化 |
法人として重要なのは、「現在はすべての派遣が許可制であり、無許可の派遣は違法」という点です。
取引先が派遣業の許可を持っているかどうかは、契約前に必ず確認すべきポイントです。
派遣先・派遣元の責任範囲と法的義務

派遣契約は、派遣元と派遣先の双方に明確な責任と義務が定められている点が特徴です。
以下に、主な役割を整理します。
派遣元の責任(雇用主)
- 雇用管理(社会保険・給与・労働時間など)
- キャリアアップ支援や教育訓練
- 派遣契約内容の明確化・遵守
派遣先の責任(業務管理者)
- 就業条件の明示(勤務時間・業務範囲など)
- ハラスメント防止措置の実施
- 安全衛生管理の共有(派遣元と連携)
また、労働者派遣には「派遣期間の制限」「同一労働同一賃金」などの規制がかかっており、知らずに違反すると指導や是正命令の対象となります。
派遣は法的責任とルールの明確さが強みでもあり注意点でもある
派遣契約は、法令で明確に定義された契約形態であり、業務指示や管理責任が明文化されている点が大きな特徴です。
しかし、SESや請負との違いをあいまいにしたまま運用すると、労働法違反やコンプライアンス問題に発展するリスクがあります。
法人として押さえておきたいポイント
- 派遣契約では指示は派遣先から行うことが前提
- 雇用は派遣元が持ち、就業環境整備は両者で連携が必要
- 法改正により、特定派遣はすでに廃止されている
- 派遣期間や待遇差是正措置など、細かな法規制が存在
「人材活用の選択肢」として派遣を採用する際は、法律知識と実務運用の両面からの準備が求められます。
客先常駐と派遣の違い

「同じ場所で働いていて、違いなんてあるの?」
そんな声が上がるほど、客先常駐と派遣は現場の見た目が似ています。
しかし実際には、指揮命令の構造・契約形態・適用法令など、根本から異なる制度です。
この章では、客先常駐と派遣が本質的にどう違うのかを明確にし、法令遵守やトラブル回避のために法人が押さえるべきポイントを整理します。
指揮命令権の所在と業務指示の違い
最大の違いは「誰が業務を指示できるか」=指揮命令権の所在です。
- 派遣契約 – 指揮命令権は派遣先(=クライアント企業)にあります。
→ 派遣先の社員が日々の業務内容・指示を直接出せます。 - SES契約(準委任契約) – 指揮命令権はSES企業(=元請け)にあります。
→ 常駐先での細かい指示は基本的にNG。あくまでSES企業経由での指示が原則です。
この違いを曖昧にすると、偽装派遣(違法行為)と見なされるリスクが高くなります。
雇用関係の有無と契約形態の違い

- 派遣 – 労働者は派遣元と雇用契約を結び、就労は派遣先。
→ 法的には「労働者派遣契約」で、労働者派遣法が適用されます。
- SES(客先常駐) – エンジニアはSES企業と雇用契約を結び、クライアントと準委任契約が締結されます。
→ 法的には「業務委託契約」の一種で、民法が適用されます。
どちらも「他社で働く」形ですが、雇用関係のない企業が業務指示を行うことの可否が分かれ道になります。
稼働内容や責任範囲の相違点
- 派遣 – 派遣先が業務範囲を定め、指示を出します。
→ 結果責任よりも「与えられた業務を遂行する」ことが求められます。
- SES – 業務遂行はあくまでSES企業が責任を持ち、成果責任はありません(準委任)。
→ 技術力や経験を活かし、能動的に業務支援を行う役割になります。
さらに、成果物を出す義務がある請負契約とは異なり、SESは“結果”より“遂行”が目的という点にも注意が必要です。
法的区分とそれぞれに適用される法律(労働者派遣法/民法など)
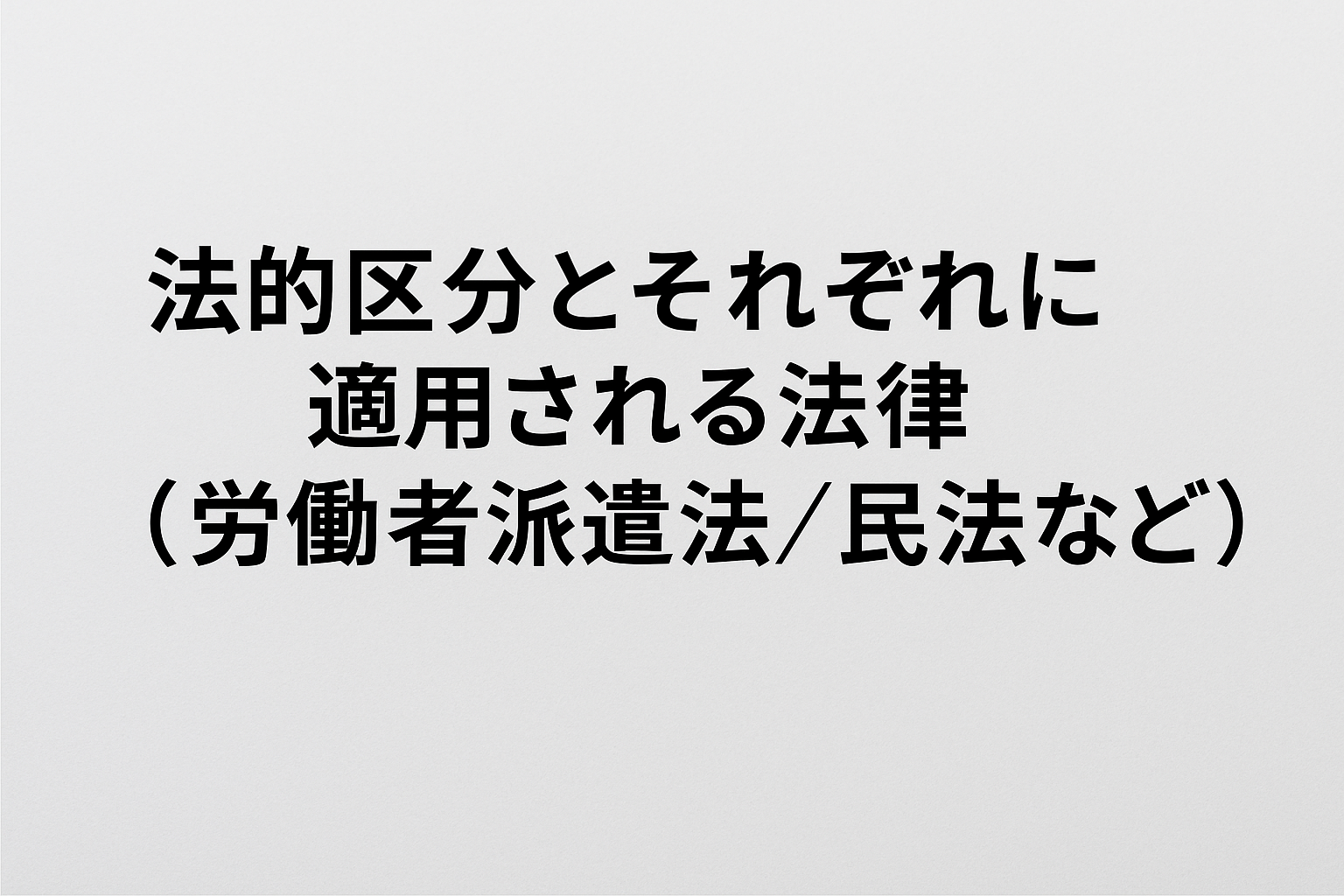
| 契約形態 | 指揮命令権 | 雇用関係 | 適用される法律 | 主な契約対象 |
| 派遣 | 派遣先 | 派遣元とあり | 労働者派遣法 | 労働力の提供 |
| SES | SES企業(派遣先は不可) | SES企業とあり | 民法(準委任契約) | 業務の遂行支援 |
| 請負 | 請負企業(成果責任あり) | 請負企業とあり | 民法(請負契約) | 成果物の納品 |
法律上の位置づけが異なる以上、契約内容・管理方法・責任分担のルールもそれぞれ異なることを念頭に置いて運用する必要があります。
「似ているようで全く違う」ことを正しく理解するのがリスク回避の第一歩
客先常駐=派遣契約とは限りません。
働く場所が同じでも、契約の根拠・責任の所在・法的ルールは大きく異なります。
本章の要点は以下の通りです。
- 指揮命令権の所在が派遣とSESでは逆であること
- 契約形態(派遣=労働契約/SES=業務委託契約)によって、適用される法律も異なる
- トラブルの多くは、この違いの理解不足から起こっている
このような違いを理解せずに契約や運用を進めると、「知らなかった」では済まされない法的リスクに直面する可能性があります。
SES契約・請負契約との違いも理解しよう

「客先常駐」と聞くと、多くの方がSESを思い浮かべるかもしれませんが、実際の契約形態がSESなのか請負なのかを正しく見極めることは非常に重要です。
契約の形式を誤れば、偽装請負や違法派遣と判断される可能性もあり、企業としての信頼や法的リスクにも関わってきます。
この章では、SESと請負の違い、そして契約形態ごとの責任・指示系統の在り方を明確に解説していきます。
SES契約の特徴(準委任契約)と指揮命令の制限
SES(システムエンジニアリングサービス)契約は、民法上の準委任契約に分類される業務委託の一種です。
エンジニアはSES企業の社員であり、クライアント先に常駐しても、業務指示はSES企業が行うという前提になっています。
SES契約の特徴
- 成果物ではなく「業務の遂行」が目的
- エンジニアの指揮命令はクライアントが直接出してはならない(※実務では形式的になりがち)
- 稼働時間ベースで報酬が支払われる(=時間準拠)
このため、現場では曖昧な状態になりやすく、実質的に指示を出してしまうと“偽装派遣”と判断されるリスクがあります。
請負契約との明確な違いと成果物責任
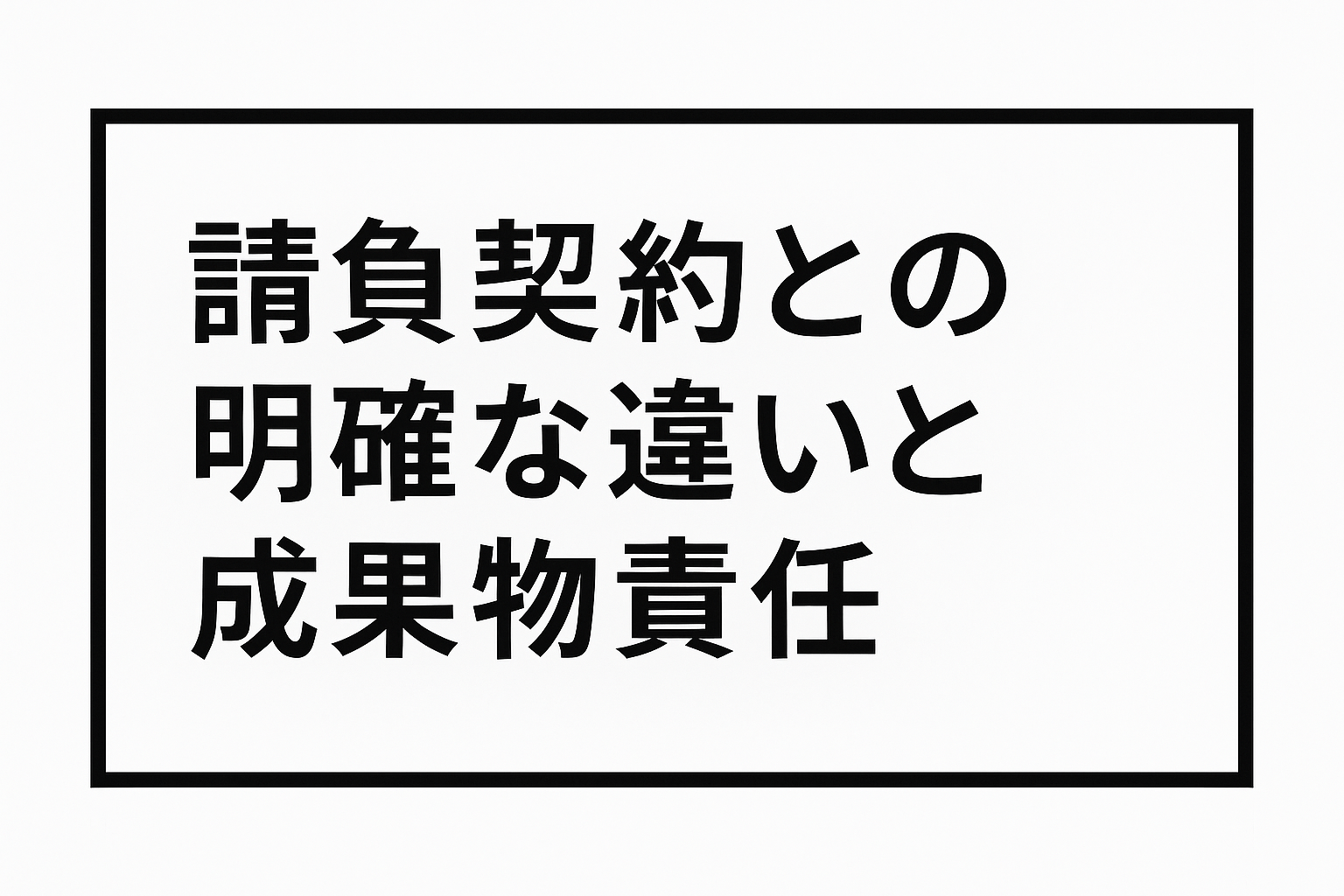
一方で、請負契約は「成果物の完成」を目的とした契約です。
業務の途中経過よりも、納品されるアウトプットに対して責任が発生する点が最大の違いです。
| 比較項目 | SES契約 | 請負契約 |
| 法的区分 | 準委任契約(民法) | 請負契約(民法) |
| 業務目的 | 作業の遂行 | 成果物の完成 |
| 指揮命令 | SES企業が指示 | 請負側の裁量で遂行 |
| 責任の所在 | 業務遂行に対する善管注意義務 | 成果物の完成責任あり |
請負契約では、たとえ常駐していたとしても業務の遂行方法や人員配置に関与されるべきではないという前提があります。
客先常駐との混同による「偽装派遣」リスクの防止
最も注意すべきなのが、SES契約や請負契約で業務委託しているつもりでも、実態が派遣と変わらないケースです。
このような場合、「偽装請負」や「違法派遣」として、労働基準監督署や厚生労働省の調査対象となる恐れがあります。
典型的なNG例
- 常駐先の担当者が直接エンジニアに業務指示を出している
- 勤務時間や休憩などをクライアントが管理している
- 複数人の入れ替えやアサインを常駐先が決定している
これらはすべて、「形式上SES・請負だが、実態は派遣」と判断される可能性のある行為です。
リスクを回避するためには、契約書の内容を明確にし、現場教育・運用ルールを徹底することが求められます。
SES・請負は「業務委託」でも責任構造と指示系統が異なる
客先常駐という同じ働き方のなかでも、SES契約と請負契約は性質が大きく異なります。
本章のポイントを整理すると以下の通りです。
- SESは業務の遂行支援、請負は成果物の完成が目的
- SES契約ではクライアントが業務指示をしてはいけない
- 請負では成果責任を負うため、業務の進め方は受託側の裁量に委ねられる
- 実態が指揮命令のある派遣と変わらない場合、偽装派遣と見なされ法的リスクを伴う
契約形態の違いを理解しないまま業務を進めると、コンプライアンス違反や行政指導のリスクを招きかねません。
法人として、形式だけでなく「実態に即した運用体制」を整えることが、信頼性のあるパートナーシップ構築に繋がります。
客先常駐と派遣のメリット・デメリット比較

企業が外部人材を活用する際、「客先常駐でのSES契約」か「派遣契約」かで迷うケースは少なくありません。
いずれも業務リソースの拡充という面で有効ですが、契約形態の違いによって、得られるメリットと抱えるリスクは大きく異なります。
この章では、法人目線で客先常駐(SESなど)と派遣のメリット・デメリットを比較し、導入の判断材料となる情報を整理します。
法人側から見たメリットと活用シーン
まずは、どちらも有効な手段であることを前提に、それぞれの強みを押さえておきましょう。
客先常駐(SES)のメリット
- 専門性の高い技術人材を即戦力として活用できる
- 上流工程や長期プロジェクトなど、高難度業務にも対応しやすい
- 作業ベースでの契約により、柔軟な調整が可能
派遣のメリット
- 業務指示を直接出せるため、マネジメントがしやすい
- コスト管理が明確(時給制や月額制が多い)
- 短期・補助業務などの即戦力確保に最適
活用シーンの一例
| シーン | 適した契約形態 |
| 高度な技術支援が必要な長期開発 | SES(常駐) |
| 繁忙期の事務サポートやヘルプデスク業務 | 派遣 |
| セキュアなシステム移行における外部協力 | SESまたは請負 |
| 単純作業のリソース補填 | 派遣 |
どちらが優れているというより、業務内容・期間・管理体制によって使い分けることが重要です。
雇用・契約の柔軟性とその制限
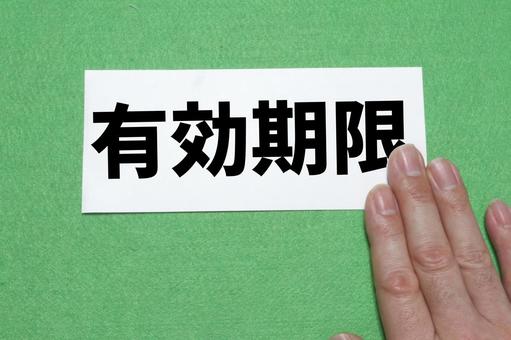
柔軟性の高さはどちらも強みですが、契約ごとに制限も存在します。
- 派遣契約では、「3年ルール」などの期間制限が存在し、同一のポジションに長期で配置できない場合があります。→ 派遣社員を同一部署で3年超勤務させると、直接雇用義務が発生するケースも。
- SES契約にはこうした年数制限はなく、長期的な参画が可能です。
→ ただし、業務指示を出せないため、実質的なマネジメントには制限があります。
また、いずれも雇用関係を直接持たないことから、正社員のような長期的成長・キャリア形成は難しいという前提を持つ必要があります。
社内文化の浸透・教育・情報管理上の課題
外部人材を社内に受け入れる際、組織文化やセキュリティ管理の観点での課題も生じます。
- 教育・研修をしにくい(特に派遣の場合、教育義務は原則派遣元)
- 社内の情報共有が制限され、属人化や業務の断絶が起きやすい
- セキュリティポリシーやコンプライアンス遵守の徹底が難しい
たとえば、顧客データを扱う部署に派遣社員やSES要員を配置する場合、NDA・アクセス権限の制限・デバイス管理など、情報漏洩リスクを徹底的に排除する体制が必要です。
これにより、「便利だから使う」のではなく、制度と業務の適合性を検討した上で導入する姿勢が求められます。
どちらにも利点と限界がある。業務目的に応じて使い分ける視点が重要
「客先常駐(SES)」も「派遣」も、業務効率を高めるための外部人材活用手段として非常に有効です。
しかし、その本質的な違いを理解せずに導入すると、現場混乱や法令違反のリスクが伴います。
要点は以下の通りです。
- SESは高い専門性と柔軟性が強みだが、指揮命令権には注意
- 派遣は業務管理がしやすい一方、期間制限や教育の制約がある
- 情報管理や社内文化の共有には、制度ごとに異なる課題がある
法人としては、単なるリソース補填ではなく、契約形態の特性を活かした「人材活用戦略」として設計することが、長期的な成果とコンプライアンスの両立に繋がります。
客先常駐や派遣を導入する際の注意点

客先常駐や派遣という形で外部人材を受け入れることは、多くの企業にとって業務効率やリソース確保に欠かせない手段です。
しかし、制度への理解が不十分なまま導入を進めると、法令違反やセキュリティ事故、現場の混乱といった深刻なトラブルに繋がる可能性もあります。
この章では、契約前・配属時・運用中の3つの視点から、法人が押さえておくべき実務上の注意点を解説します。
契約前に整理すべき指揮命令・責任範囲
最も基本でありながら見落とされやすいのが、「誰が誰に指示を出すのか」「成果責任はどこにあるのか」の整理です。
- 派遣契約の場合 – 指揮命令権は派遣先にあるため、現場での直接的な指示が可能
- SES契約の場合 – 指揮命令権はSES企業にあるため、常駐先からの直接指示はNG
この違いを曖昧にすると、偽装請負・違法派遣と判断され、行政指導や罰則の対象になるリスクがあります。
契約前には以下を明確にしておくことが重要です。
- 指揮命令権の所在
- 報告系統と連絡体制
- 作業範囲と責任の線引き
- 稼働時間や成果報告の頻度・形式
情報セキュリティや社外秘保持の体制づくり

外部人材が社内システムや顧客情報に触れる機会がある以上、情報管理体制の整備は不可欠です。
特に以下のような体制が求められます。
- 秘密保持契約(NDA)の徹底
- 業務端末の貸与・ネットワークアクセス制限の明確化
- データ保存・持ち出しに関するポリシー整備
- 社内システムへのログ管理と監査対応
一例としてクラウド環境で業務を行う場合、常駐者に適切なアクセス権限を付与しつつ、業務範囲外の情報にはアクセスできないよう制限を設ける必要があります。
現場の受け入れ体制とオンボーディング支援の重要性
受け入れ先の現場が準備不足だと、外部人材がスムーズに業務に入れず、パフォーマンス低下や定着率悪化につながります。
企業としては以下のようなオンボーディング(初期支援)を重視すべきです。
- 業務フロー・ツールの使用方法に関する初期研修
- 担当者・相談窓口の明確化
- チームとのコミュニケーション促進(朝会・進捗共有など)
- 社内規定・マナー・ルールの共有
たとえば、プロジェクト開始初日にPCが準備されていない、アクセス権限が与えられていないといったトラブルは、業務開始に大きな支障をきたします。
受け入れ側も「教育されている前提」で接するのではなく、共に働く仲間としてのフォロー体制を整えることが求められます。
受け入れの「仕組み」と「現場運用」の両方を整えてこそ成功する
客先常駐や派遣人材の受け入れは、単なる契約締結で終わるものではありません。
その後の実務運用・情報管理・社内対応の体制こそが、成果を左右する要素になります。
今回の要点は以下のとおりです。
- 指揮命令権や責任範囲を契約前に明確化すること
- 情報漏洩を防ぐためのアクセス管理・NDA・ログ監査体制の構築
- 外部人材が定着・活躍できるよう、受け入れ体制と初期支援を整える
制度上の仕組みと、現場の実務がかみ合ってこそ、リスクなく最大の成果を得ることが可能になります。
次章では、契約スタイルの選択肢をさらに深掘りし、自社に最適な導入方法を見極めるヒントをお伝えしていきます。
自社に最適な契約形態を見極めるためのポイント

人材活用の選択肢が多様化する中で、SES・派遣・請負といった契約形態を「どの場面で、どう使うか」は企業にとって重要な戦略課題です。
コスト効率やスピードだけでなく、コンプライアンスや業務成果に直結するため、単純な価格比較だけで選ぶことはリスクを伴います。
この章では、プロジェクトの特性・期間・リスク許容度に応じた契約形態の選定方法と、今後の主流となる「ハイブリッド活用」の実例を解説します。
短期プロジェクトと長期常駐の使い分け方
業務の目的や期間によって、適した契約形態は異なります。
短期プロジェクトの場合
- 繁忙期の一時的なリソース補填 → 派遣が適している
- 期間限定の検証業務やサポート業務 → **請負(成果物単位)**でコントロールしやすい
長期常駐の場合
- 上流工程の参画や継続的な運用保守が必要 → **SES(準委任契約)**で柔軟な対応が可能
- 固定チームでの常駐・長期開発 → SES+準社員化・派遣からの転換も選択肢に
ポイントは、求める成果が「成果物」なのか「人的リソース」なのかを明確にすること。
それにより、必要な責任範囲・マネジメント方法が大きく変わります。
請負・派遣・SESのハイブリッド活用例

近年では、ひとつの契約形態にこだわらず、複数の契約を組み合わせる「ハイブリッド活用」が広がりつつあります。
一例として
- メイン開発を請負で依頼しつつ、現場支援としてSESエンジニアを常駐
- 繁忙期は派遣スタッフを補強し、コア業務はSESで継続対応
- 短期PoC案件は請負、成果が見えたらSES常駐で長期運用へ移行
このように、プロジェクトフェーズごとに役割と契約形態を明確に分けることで、成果と柔軟性の両立が可能になります。
法令遵守とコンプライアンス体制の強化
どの契約形態を選ぶにしても、現場で法的リスクが発生しないよう、企業全体での運用ルールの明文化と周知が不可欠です。
対応すべき具体的な取り組みとしては:
- 契約書の雛形整備と法務チェック体制の構築
- SES・派遣・請負の違いに関する社内研修の実施
- 指揮命令権や勤怠管理に関する現場責任者への教育
- 労働者派遣法・労基法・下請法等への社内コンプライアンスチェック
IT業界では、SESを「派遣のように使ってしまう」現場が多く見受けられます。
形式と実態の乖離を防ぐことが、企業の法的安定性と信頼性維持につながります。
契約形態の理解は、リスク回避と成果最大化の土台
SES・派遣・請負は、それぞれ異なる特性と役割を持つ契約形態です。
どれが「正解」なのかではなく、「どの場面で、どの目的で、どう使うのか」こそが最も重要な視点です。
要点を整理すると
- 短期/長期・補助/中核などで目的に応じた契約形態を選ぶこと
- ハイブリッド活用で柔軟性と成果のバランスを取る
- 法令と現場運用を一致させるために、コンプライアンス意識の共有と研修体制の整備が不可欠
契約形態の選定は、単なる法務の領域にとどまりません。
それは、自社の経営基盤と信頼を守る戦略そのものです。
後は、人材リソースの多様化が進むなかで、こうした視点が企業競争力の差を生む要素となるでしょう。
こちらでは、SES企業の比較もまとめておりますので、ぜひ参考にしてください。
現場で起きやすい誤解とトラブル事例から学ぶ契約形態の選び方

派遣・SES・請負の制度を正しく理解していても、実際の現場運用では制度と実態のギャップからトラブルが発生することも少なくありません。
その多くは、「ついうっかり」の判断ミスや、「慣習で続いてきたやり方」に起因します。
この章では、実際に起きがちなトラブル事例を通じて、契約形態の選び方とリスク回避の視点を明確に解説します。
「派遣だと思っていた」が引き起こす偽装請負リスク
ある企業での例
SES契約でエンジニアを受け入れたが、現場責任者が「派遣と同じように」業務指示を出し、シフト管理や日報チェックを行っていた。
結果として、労働者派遣法違反の可能性を指摘され、是正指導を受けたという事例があります。
これは、SES契約(準委任)でありながら、実態が派遣と同様になっていた「偽装派遣」に該当したためです。
ポイントは「契約形態に沿った運用」を徹底できるか。
社内での教育不足や業務フロー未整備が、重大な法的リスクに繋がる場合があります。
指揮命令の境界が曖昧な現場での混乱事例
実務現場でありがちな例
「これはどちらの会社が指示する内容なのか」が曖昧なまま、両社の担当者から異なる要望を受け、エンジニアが混乱。
最終的に、納期や品質トラブルに発展したというケース。
これは、指揮命令権の所在が契約書上では明確になっていても、現場で共有されていない/浸透していないことが原因です。
対策として
- 契約前に、指揮命令の線引きと業務範囲を関係者間で可視化しておく
- 現場責任者・エンジニアへの**事前説明(オリエンテーション)**を徹底する
- 指示・連絡系統を図解し、定期レビューの機会を設ける
契約形態の違いは、現場でも“見える化”して共有されて初めてリスク回避につながります。
稼働中のエンジニアが突然交代する背景と対応策

「SESで業務委託していたエンジニアが、急に別の担当者に変わった」
こうしたケースも珍しくありません。
その背景には以下のような要因が考えられます。
- エンジニア側のモチベーション低下や離職
- SES企業のリソース再配置による内部調整
- 契約更新や単価見直し交渉が不調に終わった場合
対応策
- 契約時に交代条件・業務引き継ぎ方法を明文化しておく
- エンジニアの働きやすさ(常駐環境・評価制度)に配慮する
- 担当変更時には、クライアント・SES企業・本人の三者間で合意形成を行う
エンジニアの交代は業務継続に大きな影響を及ぼすため、リスク想定と柔軟な運用体制の準備が不可欠です。
「制度を知っている」だけではリスクは防げない。現場に即した実践力を
制度としての契約形態を理解していても、現場での運用や認識のズレが原因でトラブルは起きます。
今回の要点は以下のとおりです。
- 「派遣だと思っていた」という曖昧な認識が、偽装請負につながる
- 現場では指示系統を明文化・可視化することが重要
- エンジニアの交代リスクには、契約時点でルール整備と配慮が必要
トラブルを未然に防ぐには、契約時・受け入れ時・運用中の3段階で社内体制を整えることがポイントです。
契約形態の「正しい理解」に加えて、「適切に使いこなす力」こそが、法人に求められる現場対応力といえるでしょう。
契約形態の違いを正しく理解し、最適な選択でリスクを回避する

客先常駐と派遣の違いを理解することは、法令順守・現場の混乱防止・契約リスクの最小化に直結します。
本記事では、SES・派遣・請負などの契約形態ごとの違いや特徴を詳しく解説し、実際に起こりやすいトラブル事例や、導入時の注意点、契約形態の使い分け方まで網羅的に紹介しました。
特に法人担当者にとっては、以下のポイントが重要です。
- 契約ごとの指揮命令権・責任範囲・法的区分を明確に把握すること
- 自社のプロジェクト規模・期間に応じた契約形態を選ぶ戦略的視点
- ハイブリッド活用やオンボーディング支援など、現場対応力の強化
制度理解に加え、現場運用・受け入れ体制・人材管理の実務視点を持つことで、長期的な信頼関係と成果を生み出す契約運用が可能になります。
今後も契約環境が多様化する中で、柔軟かつ法令遵守を前提とした人材活用が求められます。
関連キーワード









