2025年09月14日 更新
後悔しないための選択!SESのメリットと見逃しがちなデメリットとは?
- オフィス向け

- SES(System Engineering Service)とは?
- SESの定義と基本構造(準委任契約の仕組み)
- SESと派遣・請負との違いとは
- SESが広く利用される背景と業界の現状
- SESのメリットとは?
- 即戦力エンジニアを柔軟に確保できる
- プロジェクトに応じたスキルセットの調整が可能
- 固定費を抑えた人材確保ができる
- 教育・研修コストを削減できる
- 内製チームの技術補完やスキルアップにも貢献
- SESはリスクを抑えつつ、柔軟で高効率な人材戦略を実現できる
- SESのデメリットとそのリスク
- 契約期間終了後のスキル・ノウハウが社内に残りづらい
- 業務の成果責任が曖昧になりやすい
- エンジニアの定着率が低く、モチベーションの維持が課題
- 情報漏洩やセキュリティ面のリスク
- 契約条件や単価交渉における透明性の欠如
- リスクを把握した上で、戦略的なSES活用を
- SES活用の適正判断と使いどころ
- 短期・中規模プロジェクトでの活用が有効
- 急なスキル不足・人手不足への対応策として
- 内製化移行フェーズの一時的補完としてのSES活用
- 自社に合わないケースの見極め方
- SESの運用に必要な体制とマネジメントの視点
- SESエンジニアのマネジメント体制はどうあるべきか
- 現場レベルでの運用上の注意点とは?
- リスクを最小化するための情報セキュリティ運用
- SES契約の費用構造と単価の内訳
- 時間単価制の基本と報酬の決まり方
- 見積もりに含まれるコスト項目
- エンジニアのスキルレベルごとの価格差
- 契約交渉時に注意すべきポイント
- 他の契約形態(派遣・請負)との比較
- 成果物責任の有無で分かれる契約形態
- 業務指示権と管理責任の所在の違い
- コスト構造と運用負担の比較
- 目的別の最適な契約選び
- 現場から見るSES契約のリアルな課題と乗り越え方
- 現場と営業の間にある認識のズレとは
- エンジニアの帰属意識とやりがいの両立
- クライアントの無理な要求への対応と線引き
- 人材の「使い捨て」構造を回避する工夫
- SESエンジニアのやりがいとキャリア形成の実態
- 多様な現場を経験できるスキルの幅広さ
- SESだからこそ得られる“現場力”と“適応力”
- やりがいを感じづらいときの対処法とは?
- SES活用における成功のカギと導入のベストプラクティス
- SESベンダー選定のポイントと見極め方
- 適切な管理と評価制度の設計
- 技術共有・ナレッジ蓄積のための取り組み
- 長期的な関係性構築と内製化へのステップ
- SESを導入する前に知っておくべきこと
- メリット・デメリットを客観的に整理する重要性
- 自社のリソース状況と目的に応じた最適な選択を
- 単なる「外注」ではなく、協働パートナーとしての視点を持つ
企業がITプロジェクトを推進するうえで、必要不可欠となるのがエンジニアの確保です。
中でも「SES(System Engineering Service)」は、即戦力人材を柔軟に確保できる手段として、多くの企業が採用しています。
一方で、「契約したのに成果が見えにくい」「スキルが定着しない」「社内にノウハウが蓄積されない」といったデメリットやリスクも見過ごせません。
本記事では、SES契約を検討している法人担当者の方に向けて、そのメリットとデメリットを体系的に解説します。
さらに、他の契約形態との違いや適正な活用シーン、現場で起こりがちな課題への対処法まで、実務に活かせる知識を網羅的に提供します。
「SESって本当に自社に合っているのか?」
「うまく活用して成果を出すには、どこに気をつければいいのか?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひこの記事を最後までご覧ください。
SES(System Engineering Service)とは?

企業がIT業務を外部に委託する手段の一つとして、SES(System Engineering Service)は現在、多くの現場で活用されています。
しかし「SESって派遣と何が違うの?」「実際どういう仕組みで契約するの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。
ここではまず、SESの基本的な定義と仕組み、他の契約形態との違い、そして業界で広く利用されている背景について解説します。
SESの定義と基本構造(準委任契約の仕組み)
SESとは、ITエンジニアを一定期間、企業のプロジェクトに従事させる契約形態であり、法律上は「準委任契約」に該当します。
最大の特徴は、成果物に対してではなく、エンジニアの稼働時間に対して報酬が発生する点です。
具体的には、発注企業がSES事業者に対し「一定のスキルを持つエンジニアを月160時間稼働させてほしい」と依頼し、エンジニアはクライアント企業の指示のもと業務に従事します。
このような構造により、業務内容の柔軟な変更や期間調整がしやすく、プロジェクトの進行に合わせた対応が可能となります。
SESと派遣・請負との違いとは
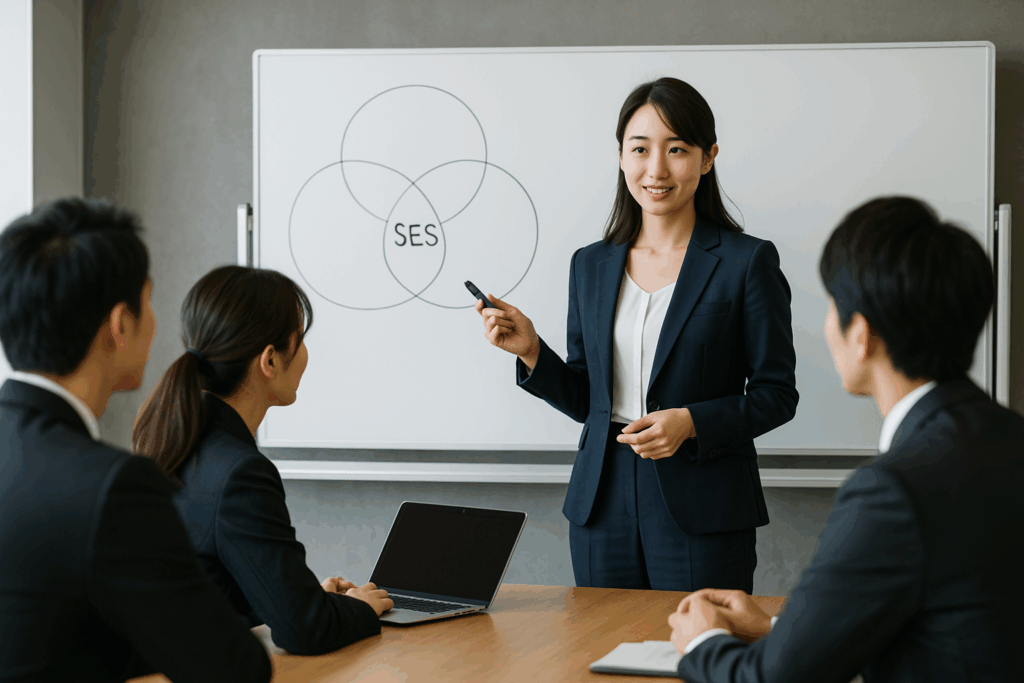
SESはしばしば派遣や請負と混同されがちですが、法的な立場や責任範囲が大きく異なります。
| 項目 | SES(準委任) | 派遣 | 請負 |
| 契約形態 | 準委任契約 | 労働者派遣契約 | 請負契約 |
| 指揮命令権 | SES事業者(現場指示は可) | 派遣先企業 | 請負会社 |
| 成果責任 | なし(業務の遂行が目的) | なし | あり(成果物に対する責任) |
| 契約の柔軟性 | 高い | やや制限あり | 低い(要件固定) |
派遣と異なり、エンジニアがクライアントの指示で動くことがあっても、正式な「指揮命令権」はSES事業者にあります。
また、請負のように成果物の納品を目的としないため、柔軟な変更やリソースの再配置が可能である点が、プロジェクト型業務に適しています。
SESが広く利用される背景と業界の現状
SESが急速に拡大した背景には、IT人材の慢性的な不足と、企業側の開発リソースの柔軟化ニーズがあります。
特に近年では、
- DX推進によるプロジェクトの増加
- 内製化支援を目的としたスポット要員の需要増
- 労働市場における即戦力人材の確保困難
といった課題に直面する企業が増え、SESを**「人材調達の選択肢」として積極的に取り入れるケースが目立ちます。
加えて、エンジニア側も「様々な現場でスキルを磨きたい」といった志向を持つことが多く、SESは供給側・需要側双方のニーズをマッチさせやすい構造になっているのです。
SESの仕組みと役割を正しく理解しよう
SESは、「業務を丸ごと依頼する」形ではなく、「人を一定期間、業務に従事させる」ための契約です。
その柔軟性と即応性から、特にプロジェクト単位の業務や人材不足への対応として重宝されています。
一方で、派遣や請負とは異なる法的な立場や責任範囲をしっかり把握することが重要です。
自社の課題や目的に照らし合わせながら、最適な契約形態を選択するための第一歩として、SESの基本理解は欠かせません。
こちらでは、SESでの派遣の仕組みや客先常駐との違いもまとめておりますので、チェックしてみてください。
SESのメリットとは?

SES契約の導入には、柔軟な人材調達と即戦力の確保という明確なメリットがあります。
プロジェクトの多様化とスピードが求められる現代のIT業務において、必要なときに必要なスキルを持つエンジニアを確保できるSESは、多くの企業にとって有効な選択肢です。
ここでは、SESがもたらす主な利点を5つの観点から整理します。
即戦力エンジニアを柔軟に確保できる
SESの最大のメリットは、即戦力となるエンジニアをスピーディーに確保できる点です。
採用活動に数ヶ月を要する自社採用と比べ、SESならば短期間で稼働可能な人材をアサインできるため、急な案件立ち上げやリソース不足時にも即応可能です。
特に、スキルマッチングを重視したSES事業者との連携によって、自社が必要とする技術領域に特化した人材をピンポイントでアサインすることができます。
プロジェクトに応じたスキルセットの調整が可能

開発プロジェクトごとに求められるスキルは異なります。
SESであれば、プロジェクトのフェーズや内容に応じて、必要な技術や経験を持つ人材を適宜入れ替えることが可能です。
たとえば、要件定義フェーズでは上流工程に強いエンジニアを、構築フェーズでは特定言語やフレームワークに精通したエンジニアを投入するなど、目的に応じたアサインが柔軟に行えます。
これは正社員だけで構成されたチームでは実現しにくい大きな利点です。
固定費を抑えた人材確保ができる
SES契約では、エンジニアの報酬は契約期間中の稼働時間に応じた変動費扱いになります。
これにより、正社員のような社会保険料や福利厚生費といった固定コストを抑えながら、必要な期間だけ人材を活用することが可能です。
この仕組みにより、プロジェクト単位での収益性管理がしやすくなり、コスト面の柔軟性を確保できます。
繁忙期と閑散期の差が大きい企業や、期間限定の業務支援が必要な企業にとっては、大きなコストメリットとなります。
教育・研修コストを削減できる

新卒採用や未経験者採用に伴う教育コストは企業にとって大きな負担です。
SESを活用することで、既に現場経験を積んだエンジニアを即戦力として迎え入れることができ、初期教育コストがほぼ不要になります。
また、スキルアップや社内研修を行う必要もないため、短期間で成果を求めるプロジェクトにおいて、研修期間を省略し即戦力を投入できる点も魅力です。
内製チームの技術補完やスキルアップにも貢献
SES人材は単なるリソースとしてだけでなく、自社エンジニアへの技術的刺激やナレッジ共有のきっかけにもなり得ます。
新しい言語や開発手法、ツールの活用法など、実務を通じて自社チームが学び、内製化の推進や技術レベルの底上げに貢献するケースも多くあります。
たとえば、新規プロジェクトでアジャイル開発の経験があるSESエンジニアがチームに加わることで、チーム全体が実践的にその手法を学び、今後の内製プロジェクトに活かされることもあります。
SESはリスクを抑えつつ、柔軟で高効率な人材戦略を実現できる
SESの導入は、単なるリソース補填ではなく、人材確保のスピード・コスト・柔軟性を同時に満たす戦略的な選択です。
プロジェクトごとのリソース最適化が可能となるだけでなく、内製チームへの技術波及効果まで期待できるため、外注と内製のバランスをとりたい企業にとって極めて有効な手段と言えるでしょう。
ただし、導入には自社の課題や目標に合わせた活用戦略が不可欠です。
次章では、SESが持つデメリットやリスクについても客観的に確認し、失敗しない導入のための視点を整理します。
SESのデメリットとそのリスク

SESは多くの利点を持つ一方で、導入前に理解しておくべきデメリットやリスクも存在します。
こうした要素を軽視してしまうと、期待していた効果が得られなかったり、社内に不満やトラブルが生じたりするケースも少なくありません。
ここでは、SESを導入する際に押さえておきたい5つのリスク要因について解説します。
契約期間終了後のスキル・ノウハウが社内に残りづらい
SESのエンジニアは、基本的に契約期間が終了すれば現場から離れます。
そのため、プロジェクトで得られた知見やノウハウが自社内に十分に蓄積されないという課題があります。
たとえば、新規システムの構築や運用プロセスの最適化をSES人材主導で進めた場合、そのエンジニアが離れた後に社内で再現できない状況が発生するリスクがあります。
これは特に、内製化を目指す企業にとって致命的な問題となりかねません。
業務の成果責任が曖昧になりやすい

SES契約は準委任契約であるため、基本的には「成果物の納品」ではなく、「業務を遂行すること」自体が契約対象になります。
これにより、成果物の品質や納期に対してSES側が責任を持たないケースも多いのが現実です。
その結果、「業務は遂行されたが期待していた成果が出ていない」「タスクはこなしているが、プロジェクトの進捗が鈍い」といった、クライアント企業側の不満が生まれやすくなります。
エンジニアの定着率が低く、モチベーションの維持が課題
SESエンジニアは、現場ごとに環境が変わることが多く、チームへの帰属意識が希薄になりやすい傾向があります。
そのため、コミュニケーションの壁や情報共有の遅れが生じやすくなり、チーム全体の生産性にも影響を与える可能性があります。
また、長期プロジェクトにおいて「単価が上がらない」「キャリアが築けない」といった理由からモチベーションが下がるケースも多く、契約期間中に離脱してしまうリスクもあります。
情報漏洩やセキュリティ面のリスク

外部人材が社内システムにアクセスする以上、情報漏洩やセキュリティ事故のリスクはゼロではありません。
特に、顧客情報や社外秘データを取り扱う現場においては、適切な権限設定や端末管理、ログの監視が不可欠です。
万が一の情報漏洩が発生した場合、企業の信用失墜や法的責任に発展する可能性があり、SES導入時にはセキュリティポリシーの徹底が求められます。
契約条件や単価交渉における透明性の欠如
SESの契約では、単価やマージンがブラックボックス化していることも少なくありません。
たとえば、同じエンジニアでもクライアントに提示される金額と実際の報酬額に大きな開きがある場合、適正価格かどうかの判断が難しいという課題が発生します。
また、契約更新や稼働時間に関する取り決めが曖昧なまま進行してしまうと、エンジニア側・発注側の双方に不信感が生まれる要因となります。
リスクを把握した上で、戦略的なSES活用を
SESは柔軟な人材調達手段として非常に有効ですが、デメリットやリスク要因を正しく理解した上で活用することが不可欠です。
成果責任の所在や、情報の蓄積、モチベーション管理、契約の透明性などは、見落とされがちなポイントです。
これらを未然に防ぐには、事前の契約設計と運用ルールの整備、そして信頼できるSESベンダーとの連携が重要になります。
SES活用の適正判断と使いどころ

SESは便利な人材調達手段ですが、どんな企業にも常に最適というわけではありません。
導入効果を最大化するためには、活用すべき状況と避けるべきケースの見極めが不可欠です。
このセクションでは、SESが特に効果を発揮するケースと、そうでないケースを明確に整理し、「うちの会社に合っているか?」という疑問に対する判断軸を提供します。
短期・中規模プロジェクトでの活用が有効
SESは短期間または限定的な期間でリソースを必要とするプロジェクトに非常に適しています。
たとえば、3〜6ヶ月の開発プロジェクトや、機能追加・改修など中規模案件では、フルタイムの正社員採用よりも柔軟で迅速な人材確保が可能です。
こうした短期プロジェクトでは、内製チームに負荷をかけすぎることなく進行できるため、スケジュールと品質のバランスを保ちやすくなるのもメリットの一つです。
急なスキル不足・人手不足への対応策として
突発的に人手が足りなくなった、あるいは特定のスキルを持つ人材が一時的に必要になった場合、SESは即戦力人材をスピーディーに補充できる有効な手段です。
例えば、あるプロジェクトでPythonエンジニアが急遽退職した場合でも、数週間以内に代替人材を確保し、業務を止めずに継続できるのがSESの強みです。
また、複数拠点やグローバル対応が必要なシステム開発では、SESを活用して現地に即した対応やリソース補強を行うことも可能です。
内製化移行フェーズの一時的補完としてのSES活用

「今後は内製化を目指したいが、すぐには人材が揃わない」という企業にとって、SESは内製化移行期間を支えるブリッジ的な存在としても活用できます。
SESエンジニアを短期的に導入しながら、同時に正社員の採用や育成を進めることで、段階的に内製体制へとシフトすることが可能です。
また、SESエンジニアと社内メンバーが並行して働くことで、現場でのナレッジ移転やスキル共有が進みやすくなるという副次的な効果も期待できます。
自社に合わないケースの見極め方
すべての企業・プロジェクトにSESが適しているわけではありません。
以下のような場合には、他の契約形態や採用手段の方が効果的な可能性があります。
- 長期的に在籍させたい人材を確保したい場合(→正社員採用が望ましい)
- 成果物の品質や納期に対して厳密な責任を求める場合(→請負契約が適切)
- 組織文化やコミュニケーションを重視したチーム構成を重んじる場合
また、社内にSES人材をマネジメントする経験者がいない場合は、人材の活用効率が下がる可能性があるため注意が必要です。
SESは“いつでも使える”のではなく“適切に使い分ける”ことが重要
SESは非常に柔軟で便利な契約形態ですが、その真価を発揮するのは状況に応じた的確な判断と運用がなされてこそです。
短期的なリソース確保、特定スキルの即時補填、内製化支援といった明確な目的がある場合には、SESは非常に効果的な選択肢となります。
一方で、成果責任や長期育成を求める場面では、他の手段も含めた全体戦略の中での位置づけが求められます。
次章では、SES契約にかかる費用の構造と、単価の見方について詳しく見ていきます。
SESの運用に必要な体制とマネジメントの視点

SESの導入においては、単に外部人材をアサインするだけでは不十分です。
技術支援の枠を超え、メンタル面のフォローやキャリア支援、さらに契約面・情報セキュリティ面に至るまで、運用体制全体を設計することが欠かせません。
偽装請負のリスクや情報漏洩リスクを未然に防ぎ、エンジニアが能力を最大限に発揮できる環境を整備するための運用・マネジメント体制について整理します。
SESエンジニアのマネジメント体制はどうあるべきか
SESのマネジメントは、以下の三層構造で考えると実務に落とし込みやすくなります。
- 現場リーダー(受け入れ企業):日々のタスクや品質の確認を担当。指示はあくまでSES会社経由で行う。
- SES企業側のリーダー:エンジニアのメンタルケア、キャリア相談、稼働状況のレビューなどを担当。
- 企業間窓口(営業担当など):契約更新や人員交代、スキル見直しの定例調整を担当。
たとえば、月1回の1on1面談で現場との相性やスキル志向、稼働時間の過不足をヒアリングし、必要に応じて現場に調整依頼を出すことが、心理的安全性の確保と定着率の向上につながります。
また、以下のような連携も重要です。
- オンボーディング時に業務範囲・期待値・報告ルートを明確にする
- 月次で品質・勤怠をレビューし、エスカレーションルールを整備する
- 半年ごとにスキルの棚卸しと人員見直し計画を策定する
現場レベルでの運用上の注意点とは?
現場でSES契約を健全に運用するためには、以下の点が非常に重要です。
- 日報・勤怠報告のルート整理
勤怠や作業報告は「エンジニア→SES企業→受け入れ企業」の順に伝えることで、直接的な管理・指示を避け、偽装請負リスクを抑制できます。
- 指揮命令系統の設計と徹底
SlackやTeamsでクライアントとエンジニアが直接DMをやり取りしないようにし、「チャンネル+三者構成(クライアント・SES窓口・エンジニア)」を標準運用にすることが望まれます。
たとえば、以下のような運用フローが有効です。
- タスク指示:クライアント→SES窓口→エンジニア
- クライアントが逸脱した場合:SES窓口が是正を依頼し、即時記録
リスクを最小化するための情報セキュリティ運用
情報漏洩を防ぐためには、契約形態に関わらず社員と同等以上のセキュリティ管理ルールが必要です。
1.アクセス権限の最小化(ロールベース設計)
- SESエンジニアには「業務に必要な最小限のアクセス権限」のみ付与
- 管理者権限や機密領域へのアクセスは原則禁止
- VDIやSaaSでのログ制御を事前に設計
2.貸与PCポリシーの徹底
- 受け入れ企業側が指定PCを貸与するか、仮想デスクトップを用意
- USB・スマートウォッチなど外部デバイスの接続を原則禁止(例外は事前申請)
3.テレワーク時の接続制御
- VPN+証明書+IP制限などゼロトラスト対応
- 時間帯制限や多要素認証も加え、「誰が・いつ・どこから」アクセスしたかを完全トレース
さらに、現場で徹底すべき細かい運用例としては以下のようなものが挙げられます。
- 席を離れるときは必ず画面ロック
- 会議室に放置される紙資料の裏返し保管ルール
- 社外持ち出し不可領域を明確化し、例外時には申請書を運用
SES運用体制の最適化は“技術・人・契約”の三位一体で進める
SESの活用を成功させるには、技術支援だけに偏らず「心理的安全性」「契約・指揮命令の整備」「セキュリティ運用の徹底」の三要素をバランスよくマネジメントする必要があります。
特に、受け入れ企業とSES企業の役割分担を曖昧にしたまま運用を始めると、偽装請負の疑い・情報漏洩・エンジニア離職の三重リスクが高まります。
これらを未然に防ぐためには、初期設計・定期レビュー・現場運用の徹底が必須です。
SESは“外部人材”ではなく、“協働パートナー”として扱うことこそが、プロジェクト成功と人材定着の鍵となります。
SES契約の費用構造と単価の内訳

SESを導入する際、多くの企業担当者が悩むのが「単価は妥当なのか?」「見積の中身がわかりにくい」といった費用に関する不透明感です。
SES契約では、時間単価制をベースとした料金体系が一般的ですが、具体的に何に対して費用が発生しているのかを把握しておかないと、契約後に想定外のコストや不満が発生するリスクがあります。
ここでは、SES契約における費用の基本的な構造と、単価の見方・交渉のポイントを整理して解説します。
時間単価制の基本と報酬の決まり方
SES契約の報酬は、エンジニア1人あたりの1時間もしくは1ヶ月の稼働時間に応じて支払う「時間単価制」が基本です。
一般的には月単価で表記され、160〜180時間の想定稼働時間をもとに金額が設定されます。
たとえば、月単価80万円で契約した場合、実際には1時間あたり4,400〜5,000円程度の単価が設定されていることになります。
この金額には、エンジニアの報酬だけでなく、ベンダー側の利益・管理費も含まれています。
見積もりに含まれるコスト項目
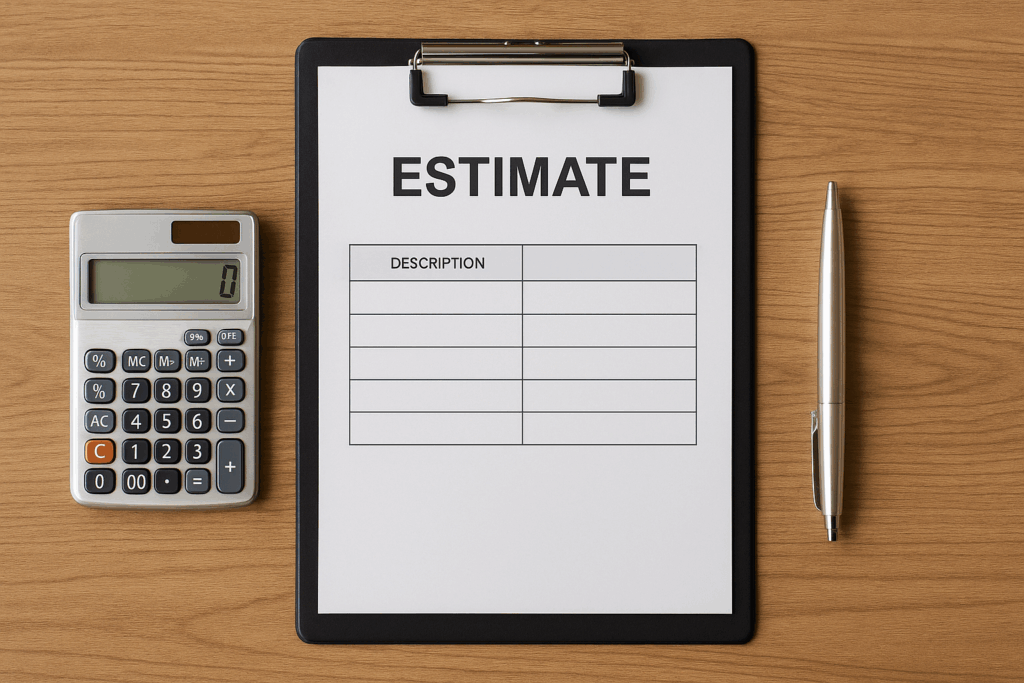
SES契約の見積書には、一見「エンジニア1名:月額○○万円」としか記載されていないことも多いですが、実際には以下のような複数の費用要素が含まれています。
- エンジニア本人の人件費(報酬)
- SESベンダーのマージン(20〜40%が目安)
- 管理・サポートコスト(営業・勤怠管理・トラブル対応など)
- 福利厚生・社会保険料(正社員SESの場合)
これらが合算されて月額費用が決定されるため、マージン率の内訳を確認することが重要です。
見積もりを鵜呑みにせず、どこまでがエンジニアへの支払いで、どこからがベンダー利益なのかを確認することで、費用の妥当性を見極めやすくなります。
エンジニアのスキルレベルごとの価格差
SESの単価は、エンジニアのスキル・経験・対応可能な業務範囲によって大きく変動します。
以下は一般的な相場感です。
| スキルレベル | 月額単価の目安(税抜) | 特徴例 |
| 初級(1〜2年) | 40万〜60万円 | テストや簡単な運用支援、既存コード修正など |
| 中級(3〜5年) | 60万〜80万円 | 基本設計・詳細設計、保守対応など |
| 上級(5年以上) | 80万〜100万円以上 | 要件定義、技術選定、リーダーポジション |
SESは「エンジニアの質=契約の成果」に直結するため、単に安さで選ぶのではなく、スキルと価格のバランスを見る視点が重要です。
契約交渉時に注意すべきポイント

SESの契約交渉では、単価だけでなく、契約内容の明確化や柔軟性も含めて交渉することが重要です。
以下の点に注意しましょう。
- 中途終了時の精算ルール(途中解約は月末締めか、日割りか)
- 稼働時間の超過・未達に対する対応(残業単価/稼働下限)
- 成果物がなくても満額支払う必要がある点を理解しておく
- 単価交渉時に、ベンダー側のマージン率や根拠を確認する
また、「高単価だからハイスキルとは限らない」という点にも注意が必要です。
スキルシートや面談を通じて、実績や得意領域を確認するプロセスを怠らないことが、ミスマッチを防ぐ鍵となります。
単価の背景を理解し、納得感ある契約を目指す
SES契約では、見積もりの裏側にある単価の構造やマージンの存在を正しく理解することが、健全な取引の第一歩です。
単価が安ければ得というわけではなく、スキル・対応力・サポート体制などの価値を踏まえた“納得できる価格”が重要。
費用だけで判断せず、契約の中身とリスクも加味してトータルで判断する視点を持つことで、SESのメリットを最大限に引き出すことができます。
次は、他の契約形態(派遣・請負)との違いを比較し、SESとの使い分けについて詳しく見ていきましょう。
SES契約でのトラブルについて法人目線でまとめているこちらの記事もおすすめ!
他の契約形態(派遣・請負)との比較

SESを検討する際に避けて通れないのが、他の契約形態である「派遣」「請負」との違いです。
一見似ているようでも、契約上の責任範囲や業務の進め方、コスト負担などが大きく異なるため、選択を誤ると「期待していた成果が得られなかった」といったミスマッチにつながります。
ここでは、それぞれの契約形態の特徴を比較しながら、プロジェクトや業務の目的に応じた使い分けの視点を解説します。
成果物責任の有無で分かれる契約形態
契約の本質的な違いは、「成果に対して責任を負うかどうか」にあります。
| 契約形態 | 成果物責任 | 主な特徴 |
| SES(準委任) | ×(業務遂行が目的) | 時間単価での人材提供。成果責任なし |
| 派遣 | ×(労務提供が目的) | 労働力の提供。企業が指示命令を出す |
| 請負 | ○(成果物の納品が目的) | 成果に対して責任を負う。仕様固定が前提 |
SESと派遣は、どちらも成果そのものには責任を持ちません。
そのため、「誰が、何を、どこまで担当するか」を明確にしておかないと、責任の所在があいまいになり、トラブルの原因になります。
一方、請負契約は納品物が契約対象となるため、品質や納期に関する契約リスクも含みます。仕様が固まり、明確な成果物がある場合に適しています。
業務指示権と管理責任の所在の違い

業務指示権の所在も、契約形態を選ぶ際の重要な判断軸です。
| 契約形態 | 指示命令権 | 管理責任 |
| SES | クライアントが実質指示(法的には受託側) | SES提供会社 |
| 派遣 | クライアントが直接指示 | 派遣元企業 |
| 請負 | 請負会社が管理・指示 | 請負会社 |
SESでは現場での業務指示がクライアントから出されることが一般的ですが、法的には指揮命令権はSES提供会社にあります。
一方、派遣契約では明確にクライアントが指揮命令権を持ち、日々の業務指示を自由に出せる点が大きな違いです。
請負は、業務管理を全て請負側が担う必要があるため、発注側は「任せきり」にしやすいものの、納品責任が発生する分、仕様変更に弱いという側面もあります。
コスト構造と運用負担の比較
契約形態ごとに、費用面と運用体制の負担にも違いがあります。
- SES – コストは中間的。指示や評価、日々の稼働確認が必要だが、柔軟な運用が可能。
- 派遣 – 比較的安価な傾向があるが、教育・管理の負担が大きい。
- 請負 – 高単価だが管理は少なくて済む。変更が発生すると追加費用がかかりやすい。
たとえば、「継続的に仕様が変わるプロジェクト」では、柔軟に対応できるSESが最も適していることが多いです。
一方で、「仕様が確定していて納品責任を明確にしたい」のであれば、請負の方が合っています。
目的別の最適な契約選び

最終的には、自社の課題・業務目的・体制に応じて契約形態を選ぶことが重要です。
以下に簡単な判断フローをまとめます。
- 柔軟な人材補強が必要/仕様変更が頻繁にある → SES
- 定常業務の補助/簡易業務の人手不足対策 → 派遣
- 明確な成果物納品/スケジュール厳守が必須 → 請負
このように、すべての業務に万能な契約形態は存在しません。
自社のプロジェクトや体制にフィットした形で使い分けることが、コスト効率と業務品質を両立させるカギとなります。
SES・派遣・請負を正しく理解し、目的に応じて賢く使い分ける
契約形態の違いを理解せずに導入を進めると、「思っていたのと違った」という結果になりかねません
特にSESは、派遣や請負との違いが微妙に見える分、適切な場面での使い分けが重要です。
企業にとって本当に必要なのは、契約形態そのものではなく、成果を最大化できる仕組みづくりです。
そのためにも、各契約の特徴と役割を正しく理解し、目的に合った戦略的な選択を行うことが成功の近道です。
現場から見るSES契約のリアルな課題と乗り越え方

契約形態や費用面でのメリットを理解した上で、SESを実際に導入・運用する現場では、理論だけでは語りきれないリアルな課題が数多く存在します。
エンジニア、営業担当、クライアント。
それぞれの立場で見えている世界にズレがあることも多く、うまく連携が取れないと、離職・トラブル・品質低下といった問題に直結するケースも少なくありません。
この章では、SES運用でよくある現場レベルの課題と、それをどう乗り越えていくべきかについて解説します。
現場と営業の間にある認識のズレとは
SESビジネスでは、エンジニアを提案・マッチングする営業担当と、実際に働く現場のエンジニアの間に「期待値のギャップ」が起きやすくなります。
営業は「早期アサイン」や「高単価確保」を優先するあまり、スキルが十分にマッチしていない案件にエンジニアを投入してしまうケースがあります。
一方で現場側は、求められるレベルと実際のスキルの乖離に苦しみ、モチベーションを失うことも。
このギャップを埋めるには、営業とエンジニアの密なコミュニケーションと、事前の情報共有の徹底が不可欠です。
スキルシートだけでなく、本人のキャリア希望や性格、過去の現場適応状況まで含めてすり合わせを行うことで、アサインの精度と満足度を高めることができます。
エンジニアの帰属意識とやりがいの両立

SESのエンジニアは、自社ではなく“常駐先”の環境で業務を行うことが多く、帰属意識を持ちづらいという問題があります。
「自分はこのプロジェクトにとって何者なのか」「発言権がない」「評価されない」という感覚に陥ると、やりがいや責任感を感じにくくなり、離職率の上昇にもつながります。
この課題に対しては、以下のような対策が有効です。
- 定期的なフォローアップ面談の実施(現場+営業+エンジニア)
- 社内表彰制度・キャリア支援など自社内での評価制度の整備
- ナレッジ共有やオンライン交流など、“社内とのつながり”を保つ仕組み
「自分は一人じゃない」と実感できる環境を整えることで、エンジニアのエンゲージメントと定着率は大きく改善します。
クライアントの無理な要求への対応と線引き
SESエンジニアは、現場でクライアントと直接やり取りする場面が多いため、立場のあいまいさから「断れない雰囲気」に巻き込まれがちです。
たとえば、「契約範囲外の業務を頼まれる」「残業前提で稼働を要求される」といったケースは、モラルやコンプライアンス上も問題になり得ます。
こうした事態を防ぐには、以下の対策が求められます。
- 契約時に業務範囲・稼働条件を明文化しておく
- 営業やマネージャーが定期的に現場状況をヒアリングする
- 必要に応じてクライアントに明確な説明・調整を行う
エンジニア任せにせず、企業としての“守る姿勢”を見せることが、信頼関係の構築にもつながります。
人材の「使い捨て」構造を回避する工夫

SESが批判されがちな要因のひとつに、「使い捨ての構造」があります。
単価重視の運用で、エンジニアが消耗品のように扱われる状況が続くと、業界全体の信用にも関わります。
これを回避するには、以下のようなアプローチが効果的です。
- 単価だけでなくスキルアップや成長支援に注目したアサイン方針
- 本人のキャリア志向とマッチする案件選定
- 稼働後も継続的なキャリアサポートを行う体制の構築
SESを「ただの労働力」として扱うのではなく、長期的な関係性を見据えた“育成型SES”として位置づけることが重要です。
現場のリアルに目を向けた運用が、SES活用の質を左右する
SES契約は、単に人材を調達する手段ではなく、人と人、会社と会社との関係構築が求められるビジネスモデルです。
現場の声を無視したままでは、どれだけ制度が整っていても成果にはつながりません。
認識のズレ、モチベーションの低下、過剰要求、消耗構造――こうした課題に真正面から向き合い、運用の質を高める取り組みを継続することが、SES活用の成功に不可欠です。
SESエンジニアのやりがいとキャリア形成の実態

SESエンジニアとしてのキャリアは「現場で揉まれて成長する」という実践型の道です。
多くの企業で「即戦力人材」として重宝される背景には、SES特有の多様な案件経験と、それを通じて培われる適応力があります。
一方で、「やりがいを感じづらい」といった声が上がるのも事実。
ここでは、SESエンジニアとして働くことの本質的な価値や、キャリアアップを実現するためのポイントを整理します。
多様な現場を経験できるスキルの幅広さ
SESエンジニアの最大の強みは、複数の現場を通じて幅広いスキルを短期間で習得できる点にあります。
一般的な受託開発や自社開発のエンジニアは、特定のプロダクトや開発フェーズに長期間携わるケースが多いのに対し、SESでは1〜2年単位でプロジェクトが変わることが一般的です。
その結果、要件定義・設計・開発・テスト・保守運用といった全工程に触れるチャンスが増え、総合的なITスキルが身につきやすい環境といえます。
また、以下のようなキャリアの積み方も可能です。
- 1年目:ヘルプデスク/保守運用(IT基礎とトラブル対応)
- 2年目:小規模開発のテスト設計・進行(工程管理)
- 3年目:要件定義フェーズに参加(クライアント折衝スキル)
このように、早期から“開発以外”の上流・下流工程を経験できるのは、SESならではの魅力です。
さらに、特定技術に偏らず、オンプレからクラウド、社内業務系からWebサービス系など技術領域を柔軟に広げられるのも特長であり、転職市場での武器になります。
SESだからこそ得られる“現場力”と“適応力”
SESエンジニアには、技術力以上に「現場での対応力」や「コミュニケーション能力」が求められます。
なぜなら、SESの配属先では社内文化、ツール、開発フローなどが都度異なるからです。
そのため、新しい現場に素早く馴染み、現場ルールを理解して動ける“順応力”が磨かれます。
さらに、クライアントの非エンジニア職と話す機会が多いため、技術を「かみ砕いて説明する力」や「橋渡し役としての調整力」も自然と育ちます。
こうした適応力・現場力の高さは、「SESで3年働いた人材は、SIerで5年経験した人材に匹敵する」と評価されることもあり、実際に以下のような差別化要因になります。
| スキル領域 | SIer3年 | SES3年 | 年収UP率 |
| 要件定義経験 | △(1社のみ) | ◎(複数社) | +25% |
| 保守運用 | ◎ | ◎(多環境) | ±0% |
| 適応力・調整力 | × | ◎ | +35% |
LinkedInやWantedlyでも「15社対応経験/VPN・光回線・社内システムに精通」など具体的に記載すれば、ヘッドハンティング率が3倍以上になる例もあります。
やりがいを感じづらいときの対処法とは?
一方で、SESに対する不満としてよく挙がるのが、「やりがいを感じにくい」「人員補填として雑務を回される」といった声です。
こうした状態を打破するには、「自分自身が主体的にキャリアを築く」という視点が不可欠です。
とくに重要なのは「三者関係の構築」です。
- クライアントと信頼関係を築く(業務外の雑談・ランチなど)
- SES自社の営業やリーダーと月次でキャリア面談を行う
- 同じ現場のエンジニアとつながりを持ち情報共有する
このように、クライアント・SES企業・自分自身の三者で現場の課題や希望を共有・交渉する仕組みを持つことが、やりがい向上と待遇改善につながります。
たとえば、下記のようなテンプレートで面談を行うと効果的です。
【SESキャリア面談の例】
- 現案件の課題共有:「非エンジニアからの直指示で混乱」
- スキルアップ希望:「次は要件定義案件に入りたい」
- 単価交渉:「実績が増えたので月単価を+3万円希望」
- 案件の方向性:「1年以上の長期案件を希望」
こうした取り組みによって、「ただの派遣」ではなく「戦略的にキャリアを構築するプロフェッショナル」としての立場を築けるのです。
SESは“下請け”ではなく“成長の土台”になる働き方
SESという働き方には誤解も多く、「やりがいがない」「下請け感が強い」といったネガティブな印象もつきものです。
しかし実際には、短期間で多様な現場を経験でき、適応力・対人スキル・全工程スキルを得られる極めて濃密なキャリア形成の場です。
やりがいを失わないためには、他責でなく“自責で選ぶ姿勢”と関係構築の工夫が重要。SESの枠にとらわれず、市場価値を高めたいエンジニアにとって、SESはむしろ成長を加速させるための「足場」になり得る選択肢といえるでしょう。
SES活用における成功のカギと導入のベストプラクティス

SESを単なる「人手の補充手段」としてではなく、事業成長に貢献する戦略的リソースとして活用するには、適切な導入と運用体制が欠かせません。
特に、ベンダーの選定や評価制度、ナレッジ蓄積の取り組みが曖昧なままでは、コストに見合った価値を得ることが難しくなります。
ここでは、SESをうまく活用して成果を上げている企業が実践している「成功のための4つのポイント」を紹介します。
SESベンダー選定のポイントと見極め方
SES導入の成否は、ベンダーの選定段階で大きく左右されます。
多くの企業が「人を供給してくれるかどうか」だけを基準にベンダーを選んでしまいますが、それでは長期的に信頼できるパートナー関係の構築は困難です。
適切なベンダーを見極めるポイントは以下の通りです。
- 提案力があるか(スキルマッチ・キャリア設計の提案)
- エンジニアの定着率や満足度を把握・開示しているか
- 案件終了後のフォローや対応体制が整っているか
- マージン率・報酬体系が透明か
単なる「人材供給業者」ではなく、現場理解と人材育成に力を入れているベンダーを選ぶことが、質の高いSES運用につながります。
適切な管理と評価制度の設計

SESエンジニアは正社員と異なり、企業側から直接人事評価されることが少ないため、成果や貢献度が見えにくくなる傾向があります。
そのため、プロジェクト運営側で明確な評価基準と管理体制を整えることが必要です。
評価制度の設計にあたっては以下が有効です。
- 成果ではなく“貢献度・対応力・改善提案”なども評価対象に含める
- 週次・月次の進捗報告をルール化し、可視化する
- クライアント・PM・エンジニアの三者評価を取り入れる
適切な管理と評価制度を整えることで、エンジニア側のやりがいや責任感も向上し、結果的にプロジェクト全体の品質が向上します。
技術共有・ナレッジ蓄積のための取り組み
SESは契約終了とともに現場からノウハウが“抜けてしまう”というリスクがあるため、ナレッジの共有と蓄積を事前に設計しておくことが重要です。
有効な施策としては以下が挙げられます。
- GitやNotion、Redmineなどを活用したドキュメントの蓄積
- 定期的なコードレビューや勉強会を通じた技術交流
- SES人材にもナレッジ共有の役割を明確に割り当てる
こうした取り組みにより、エンジニアのスキルを自社の資産として取り込むことができ、内製化への橋渡しにもなります。
長期的な関係性構築と内製化へのステップ

SESの活用を通じて中長期的に自社の開発体制を強化したい場合には、目先の単価や契約期間だけでなく、ベンダーやエンジニアとの信頼関係を築くことがカギになります。
以下のようなステップが推奨されます。
- 短期的なプロジェクトでスキルと相性を見極める
- 適性があれば継続的に案件に参画してもらう
- ナレッジ共有を通じて自社内に知識を蓄積
- 最終的には内製チームへのスムーズな移行へつなげる
このように、「外注」ではなく「協働パートナー」としてSESを位置づける視点が、継続的な成長と安定した開発体制の構築につながります。
“使う”のではなく“育てる”SES活用が成功の鍵
SESを活用する真の価値は、「必要な人材を調達すること」だけではありません。
信頼できるベンダーと協働し、現場にフィットしたエンジニアを育て、成果を共有できる関係性を築くことこそが、SES成功の本質です。
導入初期からこうした視点を持ち、評価・共有・育成といった運用面まで見据えた設計を行うことで、SESは“コスト”ではなく“成長投資”に変わります。
SESを導入する前に知っておくべきこと

ここまで、SES(System Engineering Service)の仕組み、メリット・デメリット、活用場面や成功のポイントについて詳しく解説してきました。
最後にあらためて、導入前に確認しておくべき視点や判断軸を整理しておきましょう。
メリット・デメリットを客観的に整理する重要性
SESの導入において最も重要なのは、メリットだけでなくデメリットやリスクにも目を向ける姿勢です。
たとえば、即戦力を柔軟に確保できるという利点は魅力ですが、成果責任の曖昧さやノウハウの蓄積の難しさといった側面もあります。
特に、短期的なコスト効率だけに注目してしまうと、長期的な開発体制や内製化戦略に悪影響を与えるリスクも否定できません。
導入を検討する際には、プロジェクト内容・体制・予算と照らし合わせながら、客観的に「何が得られて、何が課題になるか」を見極めることが不可欠です。
自社のリソース状況と目的に応じた最適な選択を
SESが向いているケース、そうでないケースは企業によって異なります。
そのため、「本当にSESが最適なのか?」を自社の状況に合わせて見極める視点が欠かせません。
- 社内にエンジニアが不足しているのか
- 特定スキルだけが一時的に必要なのか
- 長期的な人材育成を目指しているのか
- 成果物に対して明確な責任を求めるか
こうした条件により、SES・派遣・請負・正社員採用のどれが適しているかは変わってきます。
「何のために人材が必要なのか」を明確にすることで、失敗しない契約形態の選択につながります。
単なる「外注」ではなく、協働パートナーとしての視点を持つ

SESは単なる「外注人材」ではなく、企業のプロジェクトを一緒に前進させる“パートナー”として捉える視点が求められます。
エンジニアが安心して働ける環境を整え、技術やノウハウをチームに還元してもらえるような関係性を築くことが、成果や品質の最大化、ひいては内製化推進にもつながります。
そのためにも、信頼できるSESベンダーの選定、現場との連携、ナレッジ共有体制の整備が不可欠です。
「人材調達の一手段」ではなく、中長期的な成長戦略の一環として活用する姿勢が、これからのIT組織に求められています。
SES導入は“手段”であり、“目的”ではない
非常に有効な手段ですが、あくまで目的を達成するための“選択肢の一つ”です。
重要なのは、「人が足りないからSESを使う」ではなく、「どうすれば自社の課題が解決できるか?」という視点で契約形態を選ぶことです。
本記事で紹介したポイントを参考にしながら、自社にとって最適なSES活用戦略を見出し、後悔のない選択をしていただければ幸いです。
関連キーワード









