2025年09月14日 更新
安い折りたたみスマホの賢い買い方|失敗しない選び方ガイド
- オフィス向け
- 小売店向け
- 不動産向け
- 飲食店向け
- 学習塾向け

- 安価な折りたたみスマホのおすすめ機種
- Libero Flip|エントリー価格ながら基本性能が揃った縦折りモデル
- motorola razr 50|軽量かつ折りたたみの主流モデル
- Vivo X Fold 5|フラッグシップクオリティを抑えた価格で提供
- 折りたたみスマホの価格が下がってきた理由
- 量産効果と技術革新によるコスト低減
- 新モデル投入に伴う旧モデルの値下げ傾向
- 手に取りやすい価格帯の「FEモデル」の発売(例:Galaxy Z Flip 7 FE)
- 安いモデルを選ぶ際の押さえるべきチェックポイント
- 縦折り(フリップ型)と横折り(フォールド型)の違いとコストへの影響
- 重量や携帯性、画面サイズとのバランス
- 耐久性/防水性など基本機能の確認(価格を抑えると劣るポイントも)
- 安い折りたたみスマホを賢く購入する方法
- 旧モデルの価格が下がるタイミングを狙う(例:Pixel 9 Pro Fold の値下がり期待)
- セールやキャリアの返却プラン・割引活用
- 中古市場や整備済品の活用も選択肢
- 安い折りたたみスマホを長く快適に使うためのコツ
- ヒンジの寿命を延ばす開閉の仕方
- 画面の折り目を目立たなくする操作習慣
- バッテリー劣化を防ぐ充電ルール
- ケース・保護フィルム選びで耐久性を強化
- まとめ|安くても満足できる折りたたみスマホは選び方次第
近年、折りたたみスマホは一部のハイエンドモデルだけでなく、手に取りやすい価格帯のモデルも続々と登場しています。
かつては20万円前後が当たり前だった価格も、技術革新や量産効果により徐々に下がり、今では新品でも10万円以下、中古やセールならさらに安く手に入る時代になりました。
しかし、安いモデルだからこそ気を付けたいのが性能や耐久性の見極めです。
折りたたみ機構やヒンジ部分は精密な構造をしており、価格を抑えた機種では防水性能や耐久性、画面品質に差が出ることもあります。
この記事では、安い折りたたみスマホのおすすめ機種から選び方、購入のタイミング、そして長く使うためのコツまでをまとめて解説します。
はじめて折りたたみスマホを検討する方も、買い替えを狙う方も、失敗しないための実用的な情報をお届けします。
安価な折りたたみスマホのおすすめ機種
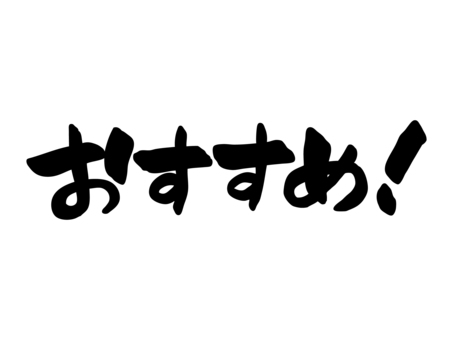
折りたたみスマホはかつて高級モデルが中心でしたが、近年は3万円台から手に入る機種も登場し、手軽にフォルダブル体験ができる時代になっています。
縦折りタイプから横開きタイプまで、多様なモデルが揃い、用途や予算に応じた選択肢が増えました。
ここでは、コスパ重視で購入できる安価な折りたたみスマホのおすすめ機種を3つ厳選し、それぞれの特徴やメリット、注意点を解説します。
Libero Flip|エントリー価格ながら基本性能が揃った縦折りモデル
ソフトバンクやY!mobile向けに展開されている「Libero Flip(リベロフリップ)」は、2024年登場の縦折りタイプで、税込3万円台から購入できる国内最安クラスのフォルダブルスマホです。
6.9インチのOLEDメインディスプレイは発色が鮮やかで見やすく、背面には1.43インチのサブディスプレイを搭載。通知や時計の表示、カメラのプレビューなど、開かなくても基本的な操作が可能です。
バッテリーは4,200mAhと余裕があり、50MPの高画質カメラも備えています。防滴性能はIP42で日常使用には十分ですが、防水や「おサイフケータイ」には非対応のため、電子決済をよく使う人は注意が必要です。
リーズナブルに折りたたみスマホを体験したい初心者層に最適な1台です。
motorola razr 50|軽量かつ折りたたみの主流モデル
モトローラの「razr 50(レイザー50)」は、2025年に発売された最新縦折りモデルで、軽量性と実用性のバランスに優れています。
重量はわずか約188gと軽く、長時間の片手操作も苦になりません。
メインディスプレイは大型で、外側には使いやすいサブディスプレイを搭載。メッセージや天気、音楽操作などが閉じたままでも快適に行えます。
内部スペックは、8GB RAMと256GBストレージ、4,200mAhのバッテリーを搭載し、日常利用やマルチタスクにも十分対応可能。
価格は税込99,800円前後ですが、セールやMVNO契約で8万円台まで下がることもあり、折りたたみスマホの“スタンダード”として高い人気を誇ります。SIMフリー対応も魅力です。
Vivo X Fold 5|フラッグシップクオリティを抑えた価格で提供
Vivoの「X Fold 5」は、横開き(ブック型)タイプのハイエンドフォルダブルで、Snapdragon 8 Gen 3、最大16GB RAM、2Kクラスの大画面ディスプレイを搭載。
カメラはZEISS監修のクアッド構成で、写真・動画撮影のクオリティはトップクラスです。
中国本土価格で約15万円前後と、同等性能を持つSamsung Z FoldシリーズやGoogle Pixel Foldよりも10万円近く安いケースもあります。
並行輸入を利用すれば日本でも入手可能ですが、正規保証や技適対応の有無には注意が必要です。
価格と性能のバランスに優れ、クリエイティブ作業やマルチウィンドウ操作を日常的に使うユーザーに特に向いています。
◇予算と用途に合わせた最適な1台を選ぼう
折りたたみスマホ市場はここ数年で大きく変化し、3万円台のエントリーモデルから15万円前後のハイエンドまで幅広くラインナップされています。
初めて折りたたみスマホを試すならコスト重視のLibero Flip、日常使いとデザイン性を両立させたいならrazr 50、最高性能を求めつつ価格も抑えたいならVivo X Fold 5がおすすめです。
購入時は、価格だけでなく対応バンド・SIMフリーの可否・保証の有無・防水やおサイフケータイ対応状況なども確認し、自分の生活スタイルや利用環境に合ったモデルを選びましょう。
折りたたみスマホの価格が下がってきた理由

かつては高級志向の象徴だった折りたたみスマホも、近年は5万円以下で購入できるモデルが登場するなど、一気に身近な存在になりつつあります。
その背景には、製造コストの低下や市場競争の激化といった複数の要因が絡み合っています。
ここでは、なぜ折りたたみスマホの価格が下がってきたのかを3つの視点から解説します。
量産効果と技術革新によるコスト低減
折りたたみスマホの初期は、ヒンジ構造や柔軟な有機ELディスプレイなど、従来にない部品や製造工程が必要で、その開発・生産コストが非常に高額でした。
しかし、SamsungやHuaweiをはじめとした大手メーカーが長年の開発を重ね、量産ラインの最適化や部品共通化が進んだことでスケールメリット(量産効果)が生まれ、1台あたりの製造コストが大幅に低下しています。
さらに、ディスプレイ技術の改良によって耐久性や歩留まり(製品の合格率)が向上し、故障や交換リスクも減少。
これにより、保証コストやアフターサービスにかかる負担も軽減され、販売価格に反映されています。
また、部品供給の多様化も価格低下を後押ししています。
初期は限られたメーカーしか生産できなかった折り曲げ可能なOLEDパネルや専用ヒンジ部品も、現在では複数企業が参入し、競争による価格引き下げが進んでいます。
新モデル投入に伴う旧モデルの値下げ傾向
スマホ市場全体に共通する傾向として、新モデルが登場すると旧モデルが値下げされるサイクルがありますが、折りたたみスマホでも同じ現象が起きています。
特にSamsung Galaxy ZシリーズやMotorola razrシリーズなどは、毎年新型が発表されるたびに前世代モデルが1〜3割ほど値下げされるケースが多く、発売から1年経たないうちに“お得な価格”で購入できるチャンスが訪れます。
加えて、キャリアやMVNOが実施するキャンペーンやMNP特価も価格低下の要因です。
契約とセットで購入すれば、大幅な割引やポイント還元が受けられ、実質的に数万円引きで手に入ることも珍しくありません。
このように、新製品の登場が旧モデルの価格を押し下げ、結果的に折りたたみスマホ全体の価格相場を引き下げる構造ができあがっています。
手に取りやすい価格帯の「FEモデル」の発売(例:Galaxy Z Flip 7 FE)
近年は、各メーカーがフラッグシップモデルの技術をベースに機能を絞り込み、価格を抑えた「FE(Fan Edition)モデル」や廉価版モデルを投入しています。
たとえば、Samsungは2025年に「Galaxy Z Flip 7 FE」を発表予定で、基本的な折りたたみ体験や主要機能は維持しながら、カメラ性能や素材を見直すことで価格を抑える戦略をとっています。
こうしたモデルはフラッグシップに比べて2〜4割ほど安く設定され、エントリー層や若年層、セカンドスマホ需要を取り込みやすくなっています。
この「手に取りやすい折りたたみスマホ」の存在は、価格の天井を押し下げると同時に、市場全体の価格帯を広げ、購入ハードルを下げる役割を果たしています。
◇価格低下は市場成熟と競争の結果
折りたたみスマホの価格が下がってきた背景には、量産効果と技術革新による製造コスト低減、新モデル投入による旧モデルの値下げ、そしてFEモデルなど廉価版の登場という3つの大きな要因があります。
これらが組み合わさることで、従来は一部のハイエンド志向ユーザー向けだった折りたたみスマホが、一般ユーザーにも手が届く製品へと変化してきました。
今後も技術進化と競争が続けば、より多くの価格帯・デザイン・機能を持つモデルが登場し、「折りたたみ=高価」というイメージはさらに薄れていくでしょう。
安いモデルを選ぶ際の押さえるべきチェックポイント

折りたたみスマホが普及し、10万円を切る低価格帯モデルも登場してきました。
とはいえ、安さだけで決めてしまうと「思ったより画面が小さい」「重くて使いにくい」「耐久性に不安がある」など、後悔につながる可能性があります。
ここでは、価格を抑えつつ満足度の高い折りたたみスマホを選ぶための3つの重要ポイントを解説します。
縦折り(フリップ型)と横折り(フォールド型)の違いとコストへの影響
折りたたみスマホは大きく分けて以下の2種類があります。
- フリップ型(縦折り)
- 閉じるとコンパクトで持ち運びやすい
- 開くと一般的なスマホサイズになる
- ヒンジ構造が比較的シンプルで製造コストが低く、低価格モデルが多い
- 例:Galaxy Z Flipシリーズ廉価版、Motorola razrベーシックモデル
- フォールド型(横折り)
- 開くとタブレットサイズの大画面
- マルチタスクや動画視聴、ビジネス用途に最適
- 構造が複雑で製造コストが高く安価なモデルは少ない
価格重視ならフリップ型、大画面重視なら中古や型落ちフォールド型という選び方が有効です。
重量や携帯性、画面サイズとのバランス
折りたたみスマホは、ヒンジや可動部の分だけ重量が増える傾向があります。
- フォールド型は250g超のモデルも多く、長時間の片手操作は負担になりやすい
- 軽量モデルはバッテリー容量が少なめで、連続使用時間が短くなる可能性がある
- フリップ型は持ち運びやすいが、表示領域は通常スマホと変わらないため分割画面やマルチタスク用途では物足りなさが出る
選び方のコツは、「用途」と「持ち運びやすさ」のバランスを見極めることです。
外出先で長時間使う場合は軽量モデル、デスクワークや動画視聴が中心なら画面の広さを優先する方が満足度は高くなります。
耐久性/防水性など基本機能の確認(価格を抑えると劣るポイントも)
低価格モデルでは、耐久性や防水性能が高価格機種より劣る場合があります。
特に注意すべきは以下の点です。
- ヒンジ耐久性 – 開閉回数の耐久試験結果や異物混入耐性を確認
- 防水性能 – 高価格帯はIPX8対応が多いが、安価モデルは簡易防滴程度が多い
- 防塵性能 – 砂やホコリの侵入を防ぐ等級が低めのことも
- ディスプレイの耐傷性 – 保護フィルムが剥がれやすい機種も存在
- バッテリー寿命 – 劣化が早いと買い替え周期が短くなる可能性
購入前にレビューや実機チェックを行うことが、長期的に満足して使い続けるためのポイントです。
◇価格と機能のバランスを見極めよう
安い折りたたみスマホを選ぶ際は、以下の3点を必ずチェックしましょう。
- フリップ型かフォールド型か(形状の違いとコスト)
- 重量と携帯性・画面サイズのバランス
- 耐久性・防水性・防塵性などの基本機能
価格が下がるほど、どこかの性能や機能が削られる傾向があります。
「何を優先し、どこを妥協できるか」を明確にすれば、コストを抑えても満足度の高い1台を選べるでしょう。
安い折りたたみスマホを賢く購入する方法

折りたたみスマホは、まだ新しいジャンルのため価格が高いイメージがありますが、購入時期や購入ルートを工夫すれば驚くほどお得に手に入れることが可能です。
新機種が毎年登場するサイクルや、販売店のセール時期、中古市場の動きをうまく活用することで、同じ予算でもワンランク上のモデルを選べることがあります。
ここでは、無理なくコストを抑えつつ満足度の高い買い物をするための具体的な方法をご紹介します。
旧モデルの価格が下がるタイミングを狙う(例:Pixel 9 Pro Fold の値下がり期待)
折りたたみスマホは新モデルが発表されるたびに旧モデルの価格が下がる傾向があります。
特にPixel FoldシリーズやGalaxy Z Foldシリーズなどの人気機種は、新型発表と同時に家電量販店やオンラインショップで大幅値下げや在庫処分セールが行われやすいのが特徴です。
例として、Pixel 9 Pro Foldの登場が予想されるタイミングでは、現行モデルが一気に値下がる可能性が高く、型落ちでも十分な性能と最新機能に近い使い心地が得られるため、コストパフォーマンス重視の人にとって絶好の買い時といえます。
セールやキャリアの返却プラン・割引活用
Amazonプライムデーや楽天スーパーセール、Black Friday、家電量販店の周年記念セールなどは、折りたたみスマホの割引率が一気に高まるチャンスです。
また、大手キャリア(docomo・au・SoftBank)では、返却プログラム(例:新トクするプログラム)を利用すると、24回払いの途中で端末を返却することで残債が免除され、実質的に半額近い負担で最新モデルを使える場合があります。
さらに、乗り換えキャンペーンや期間限定クーポンなどを組み合わせれば、想定以上に安く購入できるケースも少なくありません。
中古市場や整備済品の活用も選択肢
フリマアプリ(メルカリ・ヤフオク)や中古販売店(イオシス、ゲオモバイル)では、ほぼ未使用の美品やバッテリーの状態が良好な端末が、新品価格より2〜6割安く購入できます。
さらに、メーカーやキャリアが販売する認定整備済品(リファービッシュ品)は、新品同様の品質と保証が付くため安心感があり、価格も抑えられます。
中古や整備済み品を購入する際は、SIMフリーであるか、ネットワーク利用制限がないか、画面やヒンジの状態に問題がないかを必ず確認することが重要です。
◇タイミングと購入ルートを工夫すれば高コスパな折りたたみスマホが手に入る
折りたたみスマホは高額な製品ですが、
型落ちモデルの値下げ時期を狙うる
セールやキャリアの返却プランを活用す
中古や整備済品を検討する
様々な方法で大幅に費用を抑えながら高品質な端末を手に入れられます。
購入前には必ず複数の購入ルートと価格を比較し、自分の利用スタイルに最も合った方法を選びましょう。
こうした工夫が、長く満足できるスマホ選びにつながります。
安い折りたたみスマホを長く快適に使うためのコツ

折りたたみスマホは従来のスマホに比べて可動部が多く、ヒンジやディスプレイなど劣化しやすい部分が存在します。
特に安価なモデルでは、素材や耐久試験の水準がフラッグシップ機に比べて控えめな場合もあります。
しかし、日常の扱い方を工夫することで、寿命を延ばし、快適さを保ったまま長く使うことが可能です。
ここでは、安い折りたたみスマホを長く愛用するための4つのポイントを解説します。
ヒンジの寿命を延ばす開閉の仕方
折りたたみスマホのヒンジは精密な可動部品であり、開閉動作の積み重ねが劣化に直結します。
以下のような開閉習慣を意識するだけで耐久性は大きく変わります。
- 片手で無理にこじ開けない(両手で均等に力をかける)
- 勢いよく開け閉めせず、一定のスピードでゆっくり動かす
- 異物(砂やホコリ)が挟まった状態で開閉しない
- 不要な開閉は避け、通知確認はサブディスプレイで行う
メーカーの耐久試験は数十万回レベルでも、日常の力加減や使い方次第で寿命は大きく変わります。
画面の折り目を目立たなくする操作習慣
折りたたみスマホの特徴的な課題が、中央部分の折り目(シワ)です。
特に安いモデルでは、ディスプレイ保護層が薄かったり、素材が柔らかめだったりするため、使い方次第で目立ちやすくなります。
対策として有効な操作習慣
- 折り目部分を強く押さえたり、爪でこすらない
- スクロールやスワイプは折り目の両側から指を滑らせる
- 高温・低温環境での使用を避け、ディスプレイ素材の変形を防ぐ
- 必要に応じて純正の保護フィルムを定期交換
これらを意識すれば、見た目の美しさと操作感を長く維持できます。
バッテリー劣化を防ぐ充電ルール
安価モデルの多くはバッテリー容量がやや少なめで、劣化すると持ち時間の短さが目立ちやすくなります。以下の充電習慣で寿命を延ばしましょう。
- 充電残量20〜80%を目安に管理(フル充電やゼロ%近くは避ける)
- 長時間の充電器接続を避ける(特に高温環境)
- 急速充電は必要なときだけ使う
- 純正または認証済みの充電器・ケーブルを使用する
バッテリーは消耗品ですが、充電方法を工夫するだけで1〜2年の寿命延長が期待できます。
ケース・保護フィルム選びで耐久性を強化
折りたたみスマホは構造上、従来型よりも外部衝撃やキズに弱い部分があります。
特に安いモデルではガラス強度やフレーム剛性が控えめなことも多いため、ケースや保護フィルムの選び方が重要です。
- ヒンジ部分を保護できる専用ケースを選ぶ
- 閉じた状態でも外側画面を保護できる設計が理想
- 内側ディスプレイは純正推奨フィルムを使用(剥がれにくくタッチ感度も最適)
- 軽量ケースと耐衝撃ケースを使い分ける(外出時と自宅用で切り替え)
適切なアクセサリーは、落下時のダメージ軽減だけでなく、日常的な擦れや汚れからも本体を守ります。
◇日々の扱い方で安価モデルも長寿命に
安い折りたたみスマホは、素材や構造の耐久性が高級機種に比べて控えめなことが多いため、日常の使い方が寿命に直結します。
特に重要なのはこの4つです。
- ヒンジを優しく開閉する習慣
- 折り目部分を労わる操作方法
- 適切な充電ルールでバッテリーを守る
- 専用ケースや保護フィルムで外的ダメージを防ぐ
これらを実践すれば、低価格モデルでも3〜4年の快適利用が可能になります。
価格だけでなく、日々のメンテナンスと扱い方が、長く愛用できるかどうかの分かれ道です。
まとめ|安くても満足できる折りたたみスマホは選び方次第
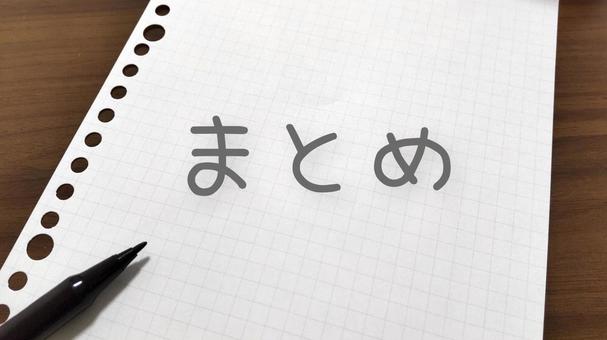
折りたたみスマホは、かつて高嶺の花だった存在から、手に届く価格帯へと進化してきました。
技術革新や量産化、新しい価格戦略モデルの登場により、以前よりも気軽に選べる時代が到来しています。
しかし、安さだけに注目してしまうと、耐久性や使い勝手に不満を感じるリスクもあります。
本記事で紹介したポイントを押さえれば、価格と品質のバランスを取りながら、失敗しない選び方が可能になります。
特に以下の点は意識しておくと安心です。
- モデルタイプの選択
縦折りか横折りかで用途や価格が変わる
- 機能の妥協点を見極める
防水性能や耐久性など、削られがちな部分を確認
- 購入タイミングと販売チャネルの工夫
旧モデルの値下げやセール、中古・整備品活用でコストダウン
- 長期使用のためのケア
ヒンジやバッテリーの劣化防止、保護フィルムやケースでの強化
安くても快適に長く使える折りたたみスマホは、知識と工夫次第で手に入れられる賢い買い物です。
自分の利用シーンやライフスタイルに合った1台を見極め、コストを抑えつつ最新のスマホ体験を楽しみましょう。
関連キーワード









